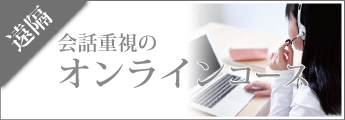スキルアップ研修の内容をピックアップするときのポイント
カテゴリ:中堅社員研修 ロジカルシンキング研修
2019年9月12日(木)

社員の能力を引き上げることが最大の目的
規模の大きな会社になればなるほど、課せられた業務の他にも、さらに能力引き上げに繋がる自己啓発を求められます。
コンピューター化が進む現代社会ですが、業務中にはどうしてもマンパワーが必要とされる業務もたくさんあり、全てをコンピューターに任せることはできません。かといって、業務スキルが充分に身についていない社員に任せることによる、想定外のダメージ発生を回避したい企業としては、社員ひとり一人の能力を引き上げることがカギとなります。
さらに、社員のスキルアップが業績アップにも繋がり、まさに一石二鳥の方法と言えるでしょう。その結果として会社から、連日の業務に追われるなか、さらに自己啓発での学びを義務付けられるといったことが起こると考えられます。
前向きに捉えれば自分にとって大いにプラス
仕事が大変なうえに、さらに自己研さんを積まなくてはならない状況に尻込みする人も多いでしょうが、自らが持つスキルをアップさせることによって社内評価が上がり、さらには上司や役員クラスの目に留まるということも考えられます。
努力によって高まった能力が大いに評価され、異例の大抜擢や昇進といったことも起こりうるかもしれません。
前向きに捉えれば、忙しい仕事の合間に研修に行くことになったとしても、上司からの評価を高めるチャンスとなるのです。
自分の力を高めるための知識の習得が、会社の業務としてタダで身に付くという発想に切り替えれば、自分自身の能力を上げることにつながるでしょう。
レベルによって必要な内容は異なるから個別のピックアップが重要
コミュニケーション能力を高めることは、全社員共通で受講することによって、かなり効率よく成果を上げることが可能ですが、それぞれのスキルを伸ばすとなると、所属部署や担当業務、さらには持っている能力に見合った研修内容を受けないと、現時点からのレベルアップは難しいと言えます。そのため、社員ごとに適した内容をピックアップすることが不可欠です。
例えば、新人に中堅社員レベルでは理解できないでしょうし、人事担当者が経理担当者に向いた内容を聞いても、さっぱり理解できず仕事にも活かせない可能性があるということです。
つまり、社員一人一人の立場や所属部署、あるいは役職付きの人ならその役職で必要とされる仕事にマッチした内容を精査する必要があるわけです。より細分化して考えると、同じ経理部門で働く人たちの間でさえも、能力によって学ぶべき内容が適しているかが分かれます。
幅広い内容の研修を用意し、社員すべてのスキルアップに繋がるように配慮することが一番で、複数の条件からのピックアップが必要なのは、こうした事情が大きいと言えるでしょう。
一人一人は大変だからまずは立場で大まかに区分するのがベスト
新人もそれぞれに多様なスキルや能力を持つ人材がおり、場合によっては、配属先がなかなか決定しない、適材適所が見当たらないという人物も混じっているかもしれません。入社1年目から3年目までは総じて若手社員という括りになり、3年目ともなるとそれぞれの能力に開きが出てくるため、ひとり一人に合ったプログラムを用意するには費用が掛かりすぎます。
そのため、大企業であればまずは立場から大まかに区分し、それぞれの立場に適した研修を受けさせるのが一般的となります。入社から3年目め程度までの若手社員グループと、3年を過ぎてバリバリ仕事ができるようになり、職場のキーパーソン的存在でありながらもまだ役職付きではない中堅社員、そして役職付きの社員といった具合に分けることで、異なるレベルの社員が混在することで起こる対抗意識といったものを避けることも可能です。
それぞれの立場に属する社員の能力に差が出るのは、どのグループに分けたとしても避けがたく発生するものであり、この差については社員ひとり一人が考えるべき課題となります。
立場によってグループ分けをしたら必要になる内容を考える
入社後の在籍3年程度といった若手社員グループに適しているのは、業務全般において必要な幅広いビジネス知識を得ることができる内容です。ビジネスパーソンとして知っておくべきことはもちろん、知識を身に付けることで仕事が捗り、押さえるべきポイントを学ぶことによって、仕事の進め方そのものが変わることもありますし、意識の変革をもたらすことにもつながるでしょう。
3年を過ぎた中堅社員は、将来的には役職付きとなり、部下を指導する立場に立つ上司になるための、コーチングと呼ばれるスキルを勉強するのが効果的です。自分自身のスキルは文句なしという高い能力を持っている人なら、近い将来部下を持つ立場へ昇格することも考えられるでしょう。
その際、管理職として部下に高いパフォーマンスを発揮させたり、何らかの問題が起こったときに自力で問題を解決する、あるいは適切な人物と共に的確に問題解決に取り組むといった能力を伸ばすためのスキルを身に着けるのに最適なのが、コーチングなのです。
役職付きになっても会社が求める能力の底上げはまだまだ続く
課長や部長といった役付き管理職ともなれば、もはやこれ以上能力の底上げは必要ないのではと考えるかもしれませんが、実際には管理職には管理職に必要な、さらなるスキルアップが求められます。
むしろ、組織のトップ、あるいは会社をけん引する人材が管理職ですので、会社が求めるレベルもより一層高くなると言えます。そんな管理職に最適なのがリーダーシップ研修でしょう。
会社は部署や組織を引っ張り、統括するすべての部下の能力を引き出すという、管理職だからこそ必要な能力を身に着けてもらいたいと考えています。そのためには立場によって異なる内容で学ぶことが、結果的にすべての社員の能力を高め、レベルアップに繋がるというわけなのです。
三つの段階に分かれて適した内容を学ぶことが大事
若手にはビジネスの何たるかを、将来は組織のリーダーとなって活躍してもらうことが期待されている中堅層にはコーチングのノウハウを、そしてトップとして組織を考える立場となった管理職には、会社の存続と業績を上げるために必要なリーダーシップを備えるための内容が適しています。求められる仕事と、その仕事に伴う責任は立場によって変わってきますので、レベルに応じた内容で学ぶことが不可欠なのは言うまでもありません。
また、順番に学ぶことによって、自分でも気付かないうちに、学びが種となり身に付いて、結果的にスキルアップに繋がることにもなるでしょう。その立場だからこそ理解し共鳴できる内容で学ぶことが、能力の底上げを実現するのは間違いなく、段階を経て徐々に成長していくのはビジネスだけでなく、さまざまなシーンに共通する要因です。
中でも大きな企業ともなれば、ひとり一人に見合った内容で学ぶのは困難になるため、まずは立場によって大まかに分類し、自分に何が求められているかを考えながら学んでもらえる内容をピックアップすることが重要です。