セルフマネジメントとは?ビジネスパーソン必須の管理能力の重要性
2015年11月15日(日)
2021年11月15日(月)
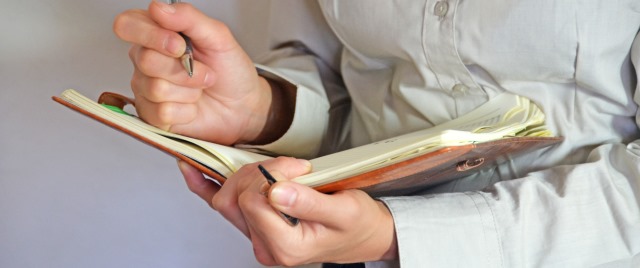
ビジネスシーンでタスク管理やモチベーション維持を意味する「セルフマネジメント」。さらに、国内においては主体的な学びという意味合いもある言葉です。ビジネスパーソンが自己管理能力を身につけると、個人にも組織にも大きなメリットが期待できます。ここ数年で働き方が大きく変化し、テレワーク導入、業務効率化が推進されたことでも、セルフマネジメント能力の向上は重要なテーマになってきました。ここでは、セルフマネジメントの意味や重要性、身につけるためのポイントをご紹介します
セルフマネジメントの意味と重要性
セルフマネジメントとは?
一般的な意味
一般的にいわれるセルフマネジメントは、英語で「self management」と表記され、自己管理という意味があります。目標達成のために、自分自身のタスクを管理したり、モチベーション維持に努めたりすることを指します。ビジネスシーンでよく使用される言葉です。
日本での捉えられ方
1970年代の高度成長期と比べると、現在のオフィス環境やそこで働く人々の姿には、時代の変化が見受けられます。サラリーマンやOLの呼称を“ビジネスパーソン”と変えざるを得ないほど、女性の総合職や管理職も珍しくなくなりました。
しかし、オフィス環境や情報機器、そして仕事自体の変貌に比して、個人のビジネススキルはさほど進化しているようには見えません。仕事の進め方に悩む人は後を絶たず、書店は夥しい数の自己啓発本やビジネス関連書籍で溢れています。
1970年代初頭のオフィスには、パソコンはおろかコピーもファックスも電卓もなく、「マネジメント」「マーケティング」「戦略」などの語句も存在しませんでした。仕事の大半は作業労働に費やされ、企業の飛躍成長は社員個々の肉体的・精神的努力に支えられていました。
この成功体験が、「皆で頑張れば何とかなる」という日本固有の属人的・精神論的な経営風土を生み、「ビジネスの基本的な知識を理論的・体系的に学ばせ、実務に応用する」という組織風土への転換を遅らせたのではないかと考えられています。日本におけるセルフマネジメントという考え方の出発点は、このような環境に端を発しています。
自らが主体的に学び、自らをマネジメントする。それが「セルフマネジメント」です。最近では多くの関連書籍も刊行されています。いわゆる自己啓発本などもその一種です。それらの書籍では、目まぐるしく変化する日々の状況や氾濫する情報の洪水のなかで、個人が自分を見失わずに当初の目標を達成するために必要なスキルとして、セルフマネジメントを取り上げています。
セルフマネジメントの重要性
セルフマネジメントと呼ばれるスキルの習得は、現在の社会においても重要な意味を持ちます。
現在の企業の新卒採用は、“大卒”であれば学部・専攻を問われません。マーケティングや企業経営を四年間学んだ学生も、夏目漱石研究に没頭した学生も同等の処遇です。
ビジネスの門外漢であろうと、異才であろうと、入社後に「ビジネス基礎教育」が計画的・システム的に組み込まれていれば良いのですが、実態は「“報・連・相”の大切さ」でお茶を濁して、あとはOJTという名の現場丸投げです。新人に適切な指導を行うことができる人がいないのです。
先述のような環境下で重要となってくるのは、いかなる状況であっても自らを「セルフマネジメント」していけるスキルでしょう。
企業や管理者からの手厚い支援が期待できず、多くの若者たちは個人でビジネス書を“斜め読み”して得た表層的な経営用語ばかりに詳しい“ビジネスパーソン”となっていきます。
しかし、セルフマネジメントを徹底しているかどうかで、表層的な知識を得るに留まるか、あるいは基礎知識を理解・習得しそれらを実務へ生かせるかが大きく分かれます。セルフマネジメントのスキルを身につけているビジネスパーソンは、己の環境に左右されず、安定して成果を上げ続けることができるはずです。
一般社員と管理者に求められるセルフマネジメントの違い
P.F.ドラッカーの名著『マネジメント』(1973)では、マネジメントを「マネジャーの5つの仕事」として以下の5項目を定義しています。
- 目標設定
- 組織化
- 動機付けとコミュニケーション
- 評価測定
- 人材開発
政府首脳や大企業の経営者から個人に至るまで、その主体と対象範囲を変えて考えれば、これほど「やるべきこと」を明確に示した定義は他にありません。
企業経営者や管理者であれば、戦略立案・ビジョンの明確化~リソース配分・個別戦術・施策の立案~意思・価値共有の推進(CSV)~進捗状況把握(PDCAやKPIなど)~社員・メンバーの育成強化となります。
では、これを個人に置き換えるとどうなるでしょうか?
主体も対象も自分自身となるのですから、「動機づけとコミュニケーション」は、「その目標が達成された時の成果や満足感を自分自身に強くイメージさせること」であり、「人材開発」は「目標達成に必要な自己研鑽努力」となります。そこに至る「具体的な実施項目の明確化」や「進捗状況把握」などの“見える化”も欠かせない要素です。
個人の健康管理や業務上の目標管理も企業・組織経営も『マネジメントの基本』に変わりはありません。換言すれば「セルフマネジメント」が確実にできれば、組織マネジメントもできるようになるということです。
セルフマネジメントが発揮する効果
あなたが一般社員の立場であるならば、まずはなにかを強く意識して学ぶことがセルフマネジメントにおいて重要です。たとえば、「マネジメント」という言葉は知っていても、「それは具体的にはどういうことを指すのか」「何をすべきなのか」を理解できなければ、知識があるとは呼べません。それは「マーケティング」「戦略」などの言葉でも同じです。
ビジネスに関する知識を学ぶ上で重要な課題は、自身の仕事への具体的な応用を常にイメージしながら、明確な『知識』として自分の中に形作ることです。知識はあくまで知識と軽視する風潮がありますが、それはあくまで学び方の問題といえます。実践の反復で知識を確実に自分のものとし、仕事に活用して結果を出すのがマネジメント力です。
一般社員がセルフマネジメントを徹底すると、上記のような高いパフォーマンスを実現できる可能性が高まるのがメリットです。さらには、自己管理能力の向上にともない、目標達成意欲や改善意欲も相乗的に高まっていくことでしょう。
あなたが管理職として組織に影響を与えていく立場ならば、上記で述べた内容の実践に加えて、部下の生産性向上への取り組みも必要です。社員一人ひとりの行動を促す要素や仕組みを業務に取り入れ、会社からの評価へ反映させることが求められます。
日本においては、企業や組織からセルフマネジメントの支援が行われにくい環境が多いのが事実です。そのため、自分自身の管轄下にある組織では、部下の学びへのモチベーションを誘発する仕組みを整えていくことが急務となるでしょう。
セルフマネジメントが上手くいかない主な理由
ストレスをため込んでいる
日頃のストレスをコントロールできずに、抱え込んでいることがないでしょうか。不安や心配事を消化できないまま悩んでも、余計な時間が過ぎていくだけです。まずは自分の精神状態を客観的にチェックし、建設的な解決策を導き出せていない状態を抜け出しましょう。
物事をネガティブに受け止めている
物事の悪い側面ばかり見てしまう。いつも憂鬱な感情に支配されている。そんな方はネガティブな考え方が習慣化していないか見直してみましょう。事実を受け止める方法によって、物事の見え方が変わります。事実は自分の気持ちと切り離し、事実として捉えましょう。
物事を俯瞰し、優先順位をつけられていない
初めに物事の優先順位を整理するのは、タスク管理の基本といえます。自己管理においても、各タスクの重要度を判断したうえでスケジュールを立て、効率の良いやり方で実行していく能力が不可欠です。ゴールへ向けて物事を俯瞰し、仕事の生産性を高めましょう。
完璧主義になりすぎている
仕事のクオリティを向上させるのは大事ですが、完璧主義になりすぎると却ってパフォーマンスが低下するおそれがあります。高すぎる目標を設定し、実現できずに自信を失うこともあるでしょう。現実的にできることの範囲内で最善を尽くすのが自己管理のコツです。
セルフマネジメント能力を身に付けるポイント
自分の役割を認識する
セルフマネジメント能力を身につけるには、まず自分が担当する業務について十分に理解しましょう。組織における自分の期待役割を把握するのが目的です。これにより、上司から求められるレベルに達しているかどうか、自分自身で認識できるようになります。
自分の課題を把握する
自分の課題を自分で見つけて解決するのは、セルフマネジメントの基本です。まずは日々の業務や生活のなかにある課題に注目することから始めましょう。課題の発見を習慣づける取り組みから始まり、最終的に解決の方向を目指せるようになると理想です。
仮説思考をする
仮説思考とは、初めに仮説を立てたうえで、検証するための情報収集や分析を行う考え方のことです。結論を出すまでの時間が限られているビジネスシーンにおいて、効果的な思考法として知られています。仮説思考をツールとして有効活用し、自己管理に役立てましょう。
ゴールから逆算してスケジュールを立てる
スケジュールを立てるとき、ゴールから逆算して考えると計画が先延ばしになるのを防げます。目標達成に必要な要素を抽出し、期日まで取り組み続けることが大切です。仕事や人生の計画を自分でコントロールするために、常に逆算の視点で考えるようおすすめします。
セルフマネジメント能力の向上を目指しましょう
セルフマネジメントとは、一般的に自己管理能力を意味します。さらに国内のビジネスシーンにおいては、主体的な学びも大事な要素のひとつといえるでしょう。
管理職と一般社員は、それぞれの立場に相応のセルフマネジメント能力が求められます。個人の、そして組織のパフォーマンスを向上させるために、自己管理能力を身につけられると理想です。
今回ご紹介したアドバイスをヒントに、セルフマネジメント能力の向上を目指しましょう。
この記事の監修者

株式会社社員教育研究所 編集部
1967年に設立した老舗の社員研修会社。自社で研修施設も保有し、新入社員から経営者まで50年以上教育を行ってきた実績がある。30万以上の修了生を輩出している管理者養成基礎コースは2021年3月に1000期を迎え、今もなお愛され続けている。この他にも様々なお客様からのご要望にお応えできるよう、オンライン研修やカスタマイズ研修、英会話、子供の教育など様々な形で研修を展開している。









