人材育成を考えたPDCAサイクルの「回し方」と「回させ方」
2016年7月29日(金)
2020年6月10日(水)
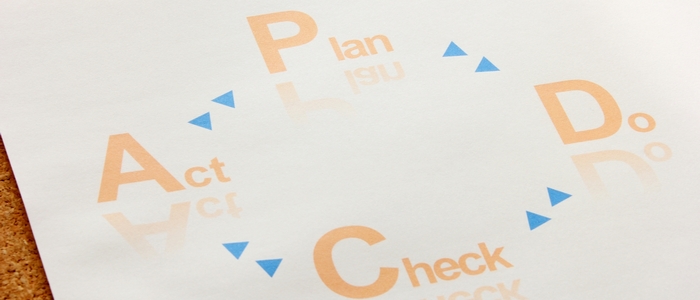
人材を得て、育成することこそ会社の将来への投資です。将来を担う人材を育成することには、それだけ時間や労力や費用をかける価値があるといえます。
しかし、人を育てるというのはそれほど簡単なことではありません。
なにも知らない子どもを教えるのとは違い、すでにたくさんの勉強や人間関係を築いてきた大人をあらためて育成するのですから、正しく効果的な育成の仕方をしないと、戦力となる人材を作り上げることは難しいとでしょう。
そこで、ポイントになってくるのがPDCAサイクルと呼ばれるものです。PDCAサイクルとは何なのでしょうか?どうすればこのサイクルをうまく回せるでしょうか?
PDCAサイクルとは?
PDCAサイクルとはPlanのP、DoのD、CheckのC、ActのAで作られている言葉です。具体的な意味としては(Plan)考え計画し(Do)実行し(Check)検証し(Act)次の行動に活かすということです。この四つのサイクルをしっかり回すことによって、人材育成をスムーズに行おうというわけです。
この四つのステップの流れは、考える→行動する→考える→行動するという順番になっています。つまりなにか言われたことをやってもらうというだけでなく、間に「考える」ということを頻繁に行わせるようになっています。
人材育成においては、この「考えさせる」ということ、しかも最終的には自主的に考えるように育てることが重要な目標となってきます。
言われたことをやる?考えてやる?
社会で広く見られる指示の出し方の一つは「これをやっておいてくれ」「言われたことをきちんとやっておいてくれ」というものかもしれません。つまりPDCAのD(Do)だけをひたすら言うようなやり方です。
こうした指導の仕方をしていると、部下は考えるというプロセスを踏まなくなります。なぜですか?言われていないことをして怒られるのが嫌だからです。言われたことだけをきちんとやればいいという思考の型になってくるわけです。
こうした状態を避けるためにも、PDCAサイクルを回すように意識しなければなりません。最初の行動の前にまず考える習慣をつけさせるのです。言われたことをただやるクセをなくし、考えて行動するクセをつけさせなければなりません。
人はなぜ考えず行動できてしまうのか?
そもそもなぜ人は「考える」というプロセスを踏まずに行動してしまうことがあるのでしょうか。
それは人が習慣の生き物だからです。人はある一定期間繰り返した行動を習慣として認識し、別段考えなくても同じ行動を取れるようになります。これは実は素晴らしい能力で、早起きやランニングなど様々な良い習慣を続ける力となります。
しかしこの同じ能力が時として考えずになんとなく行動する習慣も強化してしまうことがあります。
PDCAサイクルを回すためには、「考える習慣」を身につける必要があります。そのようにして自主的な思考とそれに続く行動を繰り返すことにより、PDCAサイクルで仕事を行っていく良い習慣が身に付きます。
考えさせるために質問する
では管理者やリーダーはどのようにして部下にもっと考えさせるように教えることができるでしょうか。
一番簡単で効果的な方法は効果的な質問を用いることです。特定の成果をあげるためにどのような方法があるか質問し、自由に考えさせることが出来るかもしれません。未熟な答えが出るとしても苛立たないようにすることが大切です。辛辣な言葉で話すなら、部下の考える力が育ちにくくなってしまいます。
また一つの行動が終わったあと、どんな点が良かったか、どんな点を改善すべきか、なぜそう思うのかなどを尋ねることによって、一人ひとりが考えて行動するよう促すことができます。このように質問をうまく用いるならばPDCAを回させることができます。
新人には十分な説明が必要
PDCAサイクルを回そうとするあまり、そして部下に考える力をつけさせようとするあまり、新人にもまったく同じクオリティを求めてしまう傾向があるかもしれません。
しかし本当の新人は、考えろと言われても考える材料がまだないので、無理に言われてもPDCAを回すことができません。
そこで新人にはある程度十分な説明による教えが必要です。そこから徐々にPDCAサイクルを回せるように巧みに指導していくことができます。
自分で物事を解決する力を身につける
PDCAサイクルを繰り返すことはなぜ大切なのでしょうか?それは社員一人ひとりが自分で考えて局面を打開したり、問題を解決したりする力を身につけることができるからです。仕事の回転率が良くなり、様々な有益なアイデアが出やすくなることでしょう。PDCAサイクルを実行すること自体が負担になると本末転倒ですので、柔軟な態度で実施していく必要があるでしょう。自社のPDCAサイクルの実施レベルを定期的に見直すことは、業務効率向上に役立つはずです。
この記事の監修者

株式会社社員教育研究所 編集部
1967年に設立した老舗の社員研修会社。自社で研修施設も保有し、新入社員から経営者まで50年以上教育を行ってきた実績がある。30万以上の修了生を輩出している管理者養成基礎コースは2021年3月に1000期を迎え、今もなお愛され続けている。この他にも様々なお客様からのご要望にお応えできるよう、オンライン研修やカスタマイズ研修、英会話、子供の教育など様々な形で研修を展開している。









