新入社員オリエンテーション資料、新人研修資料を作る際のポイントとは?
更新日:2025年12月19日(金)
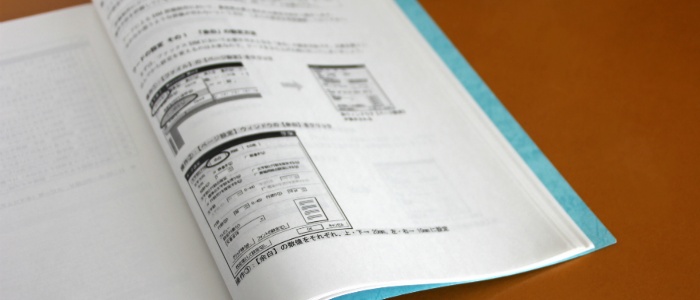
新入社員向けのオリエンテーションや研修などでは、資料を作るのが一般的です。しかし何となく前年のデータを日付などだけ変えて、あとはそのまま使ったりしていないでしょうか?新入社員の立場で考えてみると、入社書類などを除けば初めて見る会社の資料は研修資料です。ある意味で、会社の第一印象を決める要因の1つです。深く考えていない資料ではマイナスの印象を与えることとなり、定着に悪影響となりかねません。
この記事では、新入社員向けのオリエンテーションや研修の資料を作る際のポイントについてまとめます。作る際の手順から見やすいレイアウトのコツまで解説するので、企業のご担当の方はぜひ参考にしてみてください。
▼この記事でわかること
- 「オリエンテーション資料=会社を知るための地図」、「研修資料=仕事を進めるための道具
- オリエンテーション後に続く研修段階では、研修資料が「会社の第一印象」につながるため、見やすく・伝わりやすい工夫が必須
- 資料の目的は「研修の理解を助ける」と「研修後の振り返り」にあり、実務でも活用できる設計をすべき
- 新入社員研修の資料の作り方は、①研修の内容を確認②具体的に教える内容を書き出す③手書きで全体の構成をまとめる④パワーポイントなどで作成する
- 資料作成時は、各部署の意見を反映する、事例や具体例を盛り込む、研修に沿った内容になっているかを確認する、わかりやすい言葉遣いなどを意識する
- レイアウトや構成のポイントは、視覚に訴える、要点やポイントだけを押さえる、シンプルに見やすく、書き込みや作業をさせる構成にする、目次を付ける、理解度・進捗を自覚できるようにする、などが挙げられる
- 新入社員の入社オリエンテーション資料を作る目的
- 入社オリエンテーション資料に入れるべき主な項目
- 入社オリエンテーション資料の作成方法
- 入社オリエンテーション資料作成時の注意点
- 新入社員の研修資料を作る目的
- 新入社員研修の資料の作り方
- 研修資料作成時のポイント
- 自分専用マニュアルの土台を提供する
- 各部署の意見を反映する
- 実践的な演習を中心に(事例や具体例を盛り込む)
- 演習用と後から振り返りができるバイブルの二本立て
- 研修に沿った内容になっているか確認する
- 新入社員目線で作成する
- 誰もが理解できるわかりやすい言葉遣いを意識する
- 資料のレイアウト・構成のポイント
- 見やすい資料作りのコツ
- 効率よく資料を作成する方法とポイント
- よい資料で研修の効果を高めよう
- FAQ
新入社員の入社オリエンテーション資料を作る目的
新入社員は、初めての環境において会社のルールや文化、業務の流れなどがわからず、不安や戸惑いを抱えやすいものです。オリエンテーション資料を整備する目的は、まずそのような不安を事前に和らげ、会社への理解と安心感を与えることにあります。
さらに、企業理念やビジョンを共有することで、新入社員が「この会社で働く意味」を理解し、早期に会社の一員としての意識を持ってもらう狙いもあります。加えて、オリエンテーション後も振り返り可能な資料があれば、後から内容を見直すことができ、情報の見落とし防止につながります。
入社オリエンテーション資料に入れるべき主な項目
新入社員が組織の一員として活動するために必要な情報を網羅するため、資料には以下の項目を体系的に含めるべきです。
- 全体の目次と概要
- 企業のビジョン・経営理念
- 行動規範と社内規則
- 業務プロセスや部署の構造、仕事の流れ
- 新人研修のスケジュールや目標、概要
さらに、必要に応じて「よくある質問(FAQ)」や「問い合わせ先」の案内もあると、新入社員が後から困ったときに頼りやすくなります。
入社オリエンテーション資料の作成方法
効果的で活用しやすい資料を作成するためには、以下の方法で作成するのがおすすめです。
- 情報収集と整理: 企業の基本情報から各部署の詳細な業務内容まで、必要な情報を網羅的に集めます。その際、入社数年目の社員にヒアリングを行い、新人が特に不安に感じた点や疑問に思った点を把握し、資料の構成に反映させます。
- 構成とデザイン: 情報が多すぎると逆に混乱を招くため、「最初に必須で知るべきこと」に焦点を絞って情報を整理します。レイアウトは、フォントや色使いを統一し、グラフや図表、箇条書きを適度に用いながら、視覚的な分かりやすさを最優先します。
- レビュー体制: 完成後、各部署の専門担当者に内容の正確性を確認してもらうほか、新入社員と同じ視点を持つ人物に、表現の難易度や分かりやすさについてフィードバックを依頼し、最終的なブラッシュアップを行います。
入社オリエンテーション資料作成時の注意点
資料が新入社員にとって真に価値あるものとなるよう、作成時には以下の点に細心の注意を払う必要があります。
第一に、新入社員目線を徹底することです。専門用語や社内の略語は使わず、シンプルで理解しやすい言葉を選ぶべきです。もし専門用語を使わざるを得ない場合は、必ず簡単な解説を加える必要があります。
次に、情報の鮮度を保つことです。特にコンプライアンスやセキュリティ関連のルールは変化が激しいため、資料は作成したら終わりではなく、組織変更や規定の変更に合わせて定期的な見直しとアップデートを義務付けましょう。
最後に、オリエンテーション自体が一方的な講義にならないよう、資料に質疑応答や簡単なワークを促す要素を盛り込み、双方向性のコミュニケーションを意識させることが効果を高めます。
なお、新入社員を迎えるプロセスは、大きく 「会社を理解するためのオリエンテーション」 と「実務スキルを身につけるための研修」 の2段階に分かれます。
オリエンテーション資料は、会社の文化・ルール・働く上での基本情報を示す“スタートライン”であり、新入社員が安心して職場に入っていくための土台を整える役割を果たします。
一方、このオリエンテーションを終えると、多くの企業では次に新人研修が始まります。ここからは、実務に必要な知識やスキルを体系立てて習得していく段階となり、そこで重要になるのが 「研修資料」 です。つまり、
- オリエンテーション資料=会社を知るための地図
- 研修資料=仕事を進めるための道具
という位置づけであり、どちらも新入社員の自立を後押しする不可欠な要素です。ここから先の章では、オリエンテーションに続くフェーズである「新人研修における研修資料の作り方・ポイント」 を詳しく解説していきます。
研修資料を作る目的
まず初めに、そもそもなぜ研修資料を作るのか、その目的を確認しておきましょう。新人研修で資料を作る目的としては次の2つがあります。
- 研修の理解を助ける
- 研修後にも内容を確認できるようにする
それぞれの目的について確認しましょう。
研修の理解を助ける
まず初めに挙げられるのは、研修の理解を助けるという目的です。新入社員研修の内容は多岐に渡ります。内容の中にはたとえば名刺の渡し方などのように、ビジュアルなしに言葉の説明だけで理解するのは難しいものもあります。そのような内容の場合、資料で図を付けて説明すると理解しやすくなります。また売上の推移などの数字も、表やグラフにすると直感的に理解できるでしょう。
このように資料があると、説明を耳で聞くだけではわかりにくい内容も理解しやすくなります。
研修後にも内容を確認できるようにする
研修後に内容を確認できるようにすることも資料の目的の1つです。研修が終わり現場に配属されて実務に当たっていると、業務のやり方などで確認したいことが出てくる場合があります。そのとき、研修の内容が資料にまとめられていると、すぐに確認することができます。
実務に役立つ内容の研修を行うことが大前提ですが、そのうえでわかりやすく調べやすい作りにすることで、実務上の疑問を確認するという目的にかなう資料にすることができます。
新入社員研修の資料の作り方
新入社員研修の資料の作り方についてまとめます。具体的には次の手順で行います。
- 研修の内容を確認する
- 具体的に教える内容を書き出す
- 手書きで全体の構成をまとめる
- パワーポイントなどで作成する
資料作りは、研修内容が決まってから着手する場合と研修内容と同時進行で詰めていく場合とに分かれるでしょう。どちらの場合も、基本的な進め方や考え方は同じです。
では、それぞれの手順について具体的に見ていきましょう。
➀研修の内容を確認する
まず、研修の内容や目的を確認しましょう。実際の場面では、研修の内容を決めながら資料作成を同時に進めるケースもあるかもしれません。いずれにせよ、どんなことを目的にどのような内容の研修を行うのかを明確にします。目的と内容がズレている資料は役に立たないからです。
②具体的に教える内容を書き出す
研修の内容がはっきりしたら、次に研修の中で具体的に教えるスキルや知識を書き出します。できるだけ多くの事項を書き出してから、類似の内容を組み合わせたり優先度の低い事項をカットしたりします。そうすることにより、隅々まで検討することができてより練られた内容になるほか、漏れを防ぐことが可能です。
研修の設計そのものと同時進行の場合は、期間内にどれぐらいの内容を教えるのか調節することになります。この場合も初めに必要な内容を思いつくだけ書き出してから、優先度・重要度に応じて取捨選択します。
③手書きで全体の構成をまとめる
次に研修の進行・設計を反映させて、いきなり完成形を求めなくてよいので資料の構成を作っていきます。どの順序で何を教えるのかを形にしていきます。説明するのに必要なデータや図はないかも確認します。
この構成案は、いきなりパソコンで作り始めるよりは手書きで作るのがおすすめです。パソコンだとレイアウトや体裁が気になってしまい、構成そのものを作るのに集中しにくくなるからです。内容を練りながら構成を整理して完成させます。
④パワーポイントなどで作成
構成案ができたらいよいよデータを作成します。テキストベースの資料はワードを使って作成することが多くありますが、近年はパワーポイントを使ったスライド式の資料が一般的です。スライド式の場合、配布資料と研修で説明に使うレジュメの両方として使うこともできます。
詳しくは後述しますが、見やすさ・わかりやすさのためにレイアウトやフォント・図に配慮して作成しましょう。また体裁は揃えることが必須です。同じ資料内でのページごとの体裁はもちろんですが、資料が複数になる場合も資料同士の体裁も揃える方が好ましいと言えます。
研修資料作成時のポイント
次に、研修資料を作成するときのポイントとなる考え方や姿勢についてまとめます。以下の点が挙げられます。
- 自分専用マニュアルの土台を提供する
- 各部署の意見を反映する
- 実践的な演習を中心に(事例や具体例を盛り込む)
- 演習用と後から振り返りができるバイブルの二本立て
- 研修に沿った内容になっているか確認する
- 新入社員目線で作成する
- 誰もが理解できるわかりやすい言葉遣いを意識する
それぞれについて見ていきましょう。
自分専用マニュアルの土台を提供する
最初の研修で社会人としてのルールや、自社で働いていくうえで必要なことをすべて教え込もう、網羅させたいと思うかもしれません。しかしそこで分厚い資料を作っても、まだ右も左も分からず、緊張している新入社員たちは消化不良を起こすだけです。
活字が大量に並んだ資料を使うと、指導する講師もそれを時間内にこなさなくてはとプレッシャーを感じることとなりマイナスです。どんどん進めたいと思うあまりに内容が薄くなってしまったり、重要なポイントをしっかり教えられなくなってしまったりして、メリハリがつかなくなります。
おすすめのスタイルとしては、これだけは押さえておきたいというポイントを中心にシンプルにまとめることです。
そのうえで、各自が講師の話を聞いたり新人同士で話し合ったりした内容や気づきなどを自分で書き込んだり、まとめ直したりできるような作りにしましょう。入社後もずっと使える自分専用マニュアルや、その会社で生きていくための自分専用バイブルに仕上げられるようになります。
大量の文字が並んだテキストを前に、目が活字を追うのに一生懸命で思うように内容が理解できなかったり、講師の話を聞くだけで内容が入ってこなかったりする状況にならないようにしなくてはなりません。自分で書き込みをするなど、積極的で自発的な作業が加わることで、内容を咀嚼しやすくなり、自分のものとして体得していくことができます。
各部署の意見を反映する
作成にあたっては、人事部や総務部の一部のスタッフで作るのではなく、各部署の意見を反映させましょう。個別の業務にかかわる部分については、現場のスタッフの意見を聞いたり、各部署の部門長や人材教育の担当者などと連携したりして検討します。
事例が古くて今の現場を反映していない、見解が偏り過ぎているなどの不具合が生じないよう、他部署によるチェック機能を働かせると安心です。そうすることで、各部署に配属された際も、今年の新人はこういった内容は学んできている、このあたりの基本は分かっているはずだと認識しやすく、配属後の育成もしやすくなります。
重複を省くことができれば、無駄がありません。 逆に、全く触れていない部分や足りていない部分を補わずに、業務を与えて進めさせてしまうリスクも防げます。何も学んでいないのにやれといって失敗して自信を失わせたり、入社後直ぐに離職したりしてしまうリスクを抑えましょう。
実践的な演習を中心に(事例や具体例を盛り込む)
資料を使っての指導は最小限に抑え、研修の中心におきたいのはロールプレイングやディスカッションなどの実践的な演習です。そのための題材やテーマ、課題などの作り込みがとても大切になります。
実際の仕事現場で想定される内容などを、想定問題や演習問題として作成しましょう。ロールプレイングやディスカッションの題材や設問例作りが、資料作りでは一番頭を悩ませ、難しい点かもしれません。
実際にはありえない設定でロールプレイングをしたり、話し合いをさせたりしても意味がありません。新人たちに考えてほしいこと、知っておいてほしいことやこれからの仕事に役立つ課題を作成しましょう。
具体的な事例を通じて参加者自身に考えさせ、気づきを得られるよう設計することで、研修後も内容を実践に繋げやすくなります。
演習用と後から振り返りができるバイブルの二本立て
研修内容に合わせ、演習向けの題材をまとめた冊子と、職場に配属されてから必要に応じて引っ張り出せる自分専用バイブル向けのプリント冊子の2つを用意するといいでしょう。
演習向けの冊子にはロールプレイングで気づいたことや注意された内容や指摘を受けたこと、他の新人の良かった点や気になった点などどんどんメモが入ります。また、ディスカッションの内容をメモするなど、書き込みでいっぱいになるように空白部分をたくさん設けておきましょう。
もっとも、ロールプレイングでの気づきや事例を通じて学んだこと、ディスカッションで培ったアイディアやノウハウなどを、今後の仕事に生かしたいと考える新人も多いはずですし、そうあってほしいものです。そこで、振り返り用のバイブル冊子には、演習で得られた成果や結果、事例ごとの対処法や対応例などをまとめられるページも用意しておくと便利です。演習とバイブル冊子をリンクさせることで、より充実した今後の仕事に役立つ自分専用マニュアルが出来上がります。
研修に沿った内容になっているか確認する
当たり前のことではありますが、研修の資料というからには資料の内容が研修に沿っていなければなりません。資料の内容が研修の内容とかけ離れていては、後から見直そうにも意味がありません。また講師の側も予定されていた内容と異なる研修を行うと、資料が役に立たなくなってしまいます。
細かい部分についても、研修の流れと資料の流れが一致するようにしましょう。ページのスペースの問題などもあるかもしれませんが、できるだけページがあちこちに飛ぶような構成は避けましょう。
新入社員目線で作成する
新入社員の不安を軽減し、スムーズな業務開始を支援するためには、新入社員の視点に立った資料作成が不可欠です。初めての業務における不明点や社内手続きに関する疑問をあらかじめ網羅し、具体的に説明することが重要です。
例えば、「よくある質問」を設けて詳細な回答を提供したり、困った際に問い合わせできる社内連絡先を明記したりすることで、新入社員が安心して業務に取り組めるような配慮が求められます。
誰もが理解できるわかりやすい言葉遣いを意識する
研修資料は、新入社員が円滑に内容を理解できるよう、簡単でわかりやすい言葉遣いを徹底すべきです。
まだ会社の文化や用語に慣れていない新入社員にとって、「なぜ」「どうして」が腑に落ちるように、目的や背景まで丁寧に補足し、専門用語は必要に応じて説明を入れることがポイントです。
資料のレイアウト・構成のポイント
資料のページごとのレイアウトや資料全体の構成のポイントについてまとめます。以下のポイントが挙げられます。
- 視覚に訴える
- 要点やポイントだけを押さえる
- シンプルに見やすく
- 書き込みや作業をさせる構成にする
- 目次を付ける
- 理解度・進捗を自覚できるようにする
1つずつ解説していきます。
視覚に訴える
講義のスタイルにもよりますが、紙ベースの大量ページのテキストより、パワーポイントなどプレゼン資料ベースが今時の研修の基本スタイルです。
プロジェクターで投影するか、各自の席のモニターやパソコン画面に映し出すとともに、それと同じ内容のものをプリントアウトして配布しましょう。そこに各自がメモをとったり、書き加えたりしていくスタイルです。
最近の若者はネットや映像に触れる機会が多く、本や新聞などを読む機会は減っています。それに合わせて視覚に訴える、目で見て分かりやすい内容にするのがおすすめです。キャッチフレーズのような分かりやすい内容を最低限の文字で表現し、画像や図、グラフなどを多用するといいでしょう。
要点やポイントだけを押さえる
プレゼン向けのスタイルとして、プロジェクターで見せながら使用するとなれば、内容は極めてシンプルであることが求められます。
文字が大量に並ぶテキスト形式の場合、講師がそれを読んだり、新入社員に読ませながら、重要なポイントに赤線を引いてもらったり、蛍光ペンでマーキングさせたりしていくといった指導を行うことがあります。重要なポイントをわざわざマーキングして、後はざっと読むだけなら、最初からそのマーキングする部分だけを抜き出せばいいのです。メリハリをつけた部分だけをピックアップした、シンプルかつ要点や重要なポイントだけが並んだ最小限の内容でまとめましょう。
シンプルに見やすく
1ページにポイントは3つだけなど、1ページあたりの内容も少なく、シンプルにして、書き込める場所が多い構成のほうがベターです。1ページで伝えることは1つという意見もよく聞かれるほどです。ただし要点やポイントだけをピックアップしても、それを凝縮し過ぎてはいけません。
今時の新入社員は大学の授業でも板書もせず、教授が黒板に書いた内容をスマホで撮影してメモするような世代です。最近の若い社員を中心に会議の内容も、ホワイトボードに書いた内容をスマホで撮影して終わりという姿をよく見るようになったのではないでしょうか。
今時のやり方はNGというのではなく、時代の流れや今時世代の若者に合わせて、彼らが入りやすく、受け止めやすいスタイルにしていくのも1つの方法です。そうすることで消化不良を起こしたり、全く興味を示さず、せっかくの研修時間を無駄に過ごさせてしまったりすることがなくなります。
ポイントを押さえたシンプルスタイルを提供することで、新人に習得してほしいことや理解してもらいたいことをしっかり伝えていくことができるでしょう。
書き込みや作業をさせる構成にする
内容を最小限のシンプルにしたうえで、そこに肉付けをしていく作業をさせましょう。自分なりに理解した内容でまとめていくことで、各新入社員のもとでテキストが完成するイメージです。ただ講師の話を聞いているだけ、テキストやマニュアルを目で追っていくだけでは、集中力も途絶え、覚えてほしいことも身につきません。
大切な内容そのものをしっかりと習得できる効果が期待できるだけではありません。話を聞いて要点をまとめたり、要約したりする作業を通じて、これからの仕事で必要となる、まとめる力や論理力、報告する能力なども同時に育成されていきます。ビジネスパーソンとしての必須スキルも同時進行で磨けるので、一石二鳥です。
目次を付ける
資料には、冒頭に目次を付けましょう。利便性を高めるためで、該当部分を探しやすくすることで自分のマニュアル・バイブルとして活用しやすくなります。もちろんページには数字を振っておきましょう。
また目次は研修内容の一覧にもなり、全体を一目で把握することができます。研修前にはこれから何を学ぶのかのイメージが持ちやすくなり、研修後にはどんなことを学んだのかを振り返りやすくなります。
理解度・進捗を自覚できるようにする
理解度や進捗を自覚できるような構成にすることもポイントです。内容ごとに理解度や達成度のチェック項目を付したり、一問一答などの問題を付けたりすると理解度を自覚できます。また、学習している内容が研修内容全体のどこに位置するかを示すと進捗がわかります。
あるいは学習内容がどのような業務に必要かわかるようにすることも効果的です。独り立ちや戦力化にどの程度近づいているのか、自力でイメージしやすくなるからです。何ができるようになっているのか意識することは自信につながり、何ができないのか知ることは問題解決の第一歩となります。
見やすい資料作りのコツ
さらに具体的に、見やすい資料を作るためのコツについて解説します。以下の点が挙げられます。
- フォントはルールを決めて使い分ける
- 色使いはメイン+アクセントの2色
- 余白を作る
- 関係ある内容は近くに記載する
- 図やイラストの位置を揃える
上記の点について、すべてのページで同じルールにのっとってまとめます。見やすくなるのに加えて統一感・安定感が醸しだされて、内容に集中しやすくなる効果もあるからです。とくに担当者でページを分担して作成するときは、ルールを徹底する必要があります。
では、それぞれについて具体的に見ていきましょう。
フォントはルールを決めて使い分ける
フォントはルールを決めて使い分けましょう。ここでの「フォント」には、書体やサイズ、太字や下線などの文字装飾を含みます。
資料には、タイトル・見出し・本文・注釈などの要素があります。全てのページで、同じ要素は同じフォントを使いましょう。
一般に、書体はゴシック系が見やすいとされます。また注釈は見出しや本文より文字のサイズを小さくしてメリハリを付けます。サイズの比率は「ジャンプ率」と呼ばれ、ジャンプ率が高い(=大小差が大きい)ほど見やすい印象になります。強調したいときも、太字にするのか下線を使うのか、あるいは色を変えるのかなどルールを統一します。
色使いはメイン+アクセントの2色
色遣いは、(白・黒のほかは)テーマカラーとなるメインの1色とアクセントの1色の計2色を基本としましょう。使う色が多すぎると散漫な印象になり、どこが重要か伝わりにくくなるほかそもそも見にくくなります。使う色をしぼることで統一感が生まれます。
アクセントカラーはメインカラーの同系色ではなく正反対に当たる「捕色」と呼ばれる色を選ぶと、使った部分を際立たせることができます。もちろん色を使い分けるルールも統一します。
余白を作る
意識的に余白を作るように心がけましょう。すべての文字を大きくした方が読みやすいのではないかと思うかもしれません。しかし余白がないと圧迫感が生まれたり区切りがわかりにくくなり、結果的に見づらくなります。
前述した文字のジャンプ率や書体・文字装飾などとも関わりますが、余白が少ないことは重要なポイントをわかりにくくする原因です。余白を意識的に作りましょう。余白によって見やすくなるほか、気づきなどを書き込むスペースにもなります。
関係ある内容は近くに記載する
関係のある内容は近くに記載し周囲に余白を作りましょう。そのようにレイアウトすることでグループに見えるようになり、要素間の関係を視覚的にイメージさせることができます。その結果、関係のある内容・別の内容とが直感的に理解できるようになります。
反対に、関係のない内容は離してレイアウトしないと紛らわしくなり、誤解の原因になる可能性があります。
テキストだけでなく、イラストやグラフ・図も同じルールで配置しましょう。
図やイラストの位置を揃える
図やイラストを同じページに複数記載する場合、左右に並べるときは高さを、上下に並べるときは左右の位置を揃えましょう。規則的な配置によって安定感が生まれます。もちろん図やイラストの大きさも統一します。グラフや表も同様です。
そのほかテキストについても、タイトルや見出しなど各要素の位置は統一しましょう。基本的なレイアウトはテンプレート化することをおすすめします。
効率よく資料を作成する方法とポイント
効率よく資料を作成する方法とポイントについてまとめます。以下の方法があります。
- 公開されている資料を流用する
- 既存のマニュアル・HPなどを流用する
- 外注する
それぞれについて具体的に見ていきます。
公開されている資料を流用する
まず、公開されている資料を流用する方法があります。インターネットで検索すると、様々な資料が公開されています。ほとんどは連絡先などの登録が必要ですが、無料でダウンロードが可能です。そういった資料で使えそうなものを見つけて流用すれば、一から作成するよりも少ない労力で資料が作成できます。
内容はいろいろな種類がありますが、ビジネスマナーなど普遍的で汎用性の高い内容ほど流用に適しているでしょう。ただしその場合も必要に応じて自社向けにアレンジすることが必要です。もちろん企業理念など個別的な内容には向きません。
既存のマニュアル・HPなどを流用する
自社ですでに用意しているマニュアルやHPがあれば、資料に流用することができます。マニュアルや経営方針・企業理念などは企業独自の内容になりますが、そういった独自の内容に向く方法です。
HPは、自社の説明部分などの文面が資料作りに役立ちます。作業マニュアルも、未経験者向けに解説をプラスすべき部分があるかもしれませんが、文面などはほぼそのまま流用できるでしょう。ただしいずれもレイアウト・体裁は整える必要があります。
外注する
資料作りを外注するという方法もあります。研修を行っている会社に依頼する場合と、資料作成代行業者で研修資料に対応しているところに依頼する場合に分かれます。いずれも業者によって対応できる内容が異なるので、事前に確認しておくことが必要です。
内容によっては、材料を用意したり構成を指定したりしなければならないことがあるので注意しましょう。
よい資料で研修の効果を高めよう
よい資料が準備できれば、研修の理解が深まるほか研修後にも役立ちます。また新入社員の第一印象もよくなり、順調なスタートを切るきっかけ作りにも効果が期待できます。内容・構成・レイアウトなどのポイントを押さえつつ、研修に合った資料を用意しましょう。
ただし確かに資料作りも研修を成功させる大きな要素の1つですが、資料作りの負担が大きすぎるとほかの部分が手薄になってしまう可能性もあります。資料作りだけでなく、研修自体も外注できるものは外注してしまうということも選択肢として検討する価値があります。
もし新入社員研修をはじめ研修の外注を考えているのなら、まずは私ども社員教育研究所にご相談ください。最適なプランをご提案させていただきます。このページの最上部と最下部に電話番号と資料請求のリンクボタンがあります。そちらからお気軽にご連絡ください。
FAQ
新入社員研修資料の作成で最も重要なポイントは何ですか?
「見やすさ」「わかりやすさ」「実務で活用できること」を意識することが重要です。
新入社員オリエンテーション資料を作成する目的は何ですか?
1つは、多岐にわたる研修内容を新入社員が視覚的に理解しやすくすること。
もう1つは、研修後も内容を振り返り、実務で活用できるようにするためです。資料は会社の第一印象にもなり、新入社員の定着にも影響します。
新入社員研修資料のレイアウトや構成で特に重要なポイントは何ですか?
視覚に訴え、要点をシンプルにまとめることが重要です。また、新入社員が書き込みや作業ができる構成にすることで、主体的な学習を促します。
その他、目次を付けて利便性を高めたり、理解度や進捗を自覚できるような仕組みを取り入れたりすることも有効です。
この記事の監修者

株式会社社員教育研究所 編集部
1967年に設立した老舗の社員研修会社。自社で研修施設も保有し、新入社員から経営者まで50年以上教育を行ってきた実績がある。30万以上の修了生を輩出している管理者養成基礎コースは2021年3月に1000期を迎え、今もなお愛され続けている。この他にも様々なお客様からのご要望にお応えできるよう、オンライン研修やカスタマイズ研修、英会話、子供の教育など様々な形で研修を展開している。









