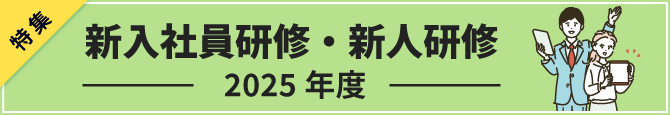新人・新入社員によくある失敗の傾向と新人を成長させる指導・研修のポイント
更新日:2025年10月20日(月)

新入社員の採用とその後の教育の良し悪しで、会社の将来は大きく左右されます。そこでどの企業も多くのリソースを費やしますが、残念ながら期待外れの結果で終わる場合もあります。採用後に大化けする良い意味での期待外れもありますが、悪い場合には大きな損失を生みます。
1つは金銭的な損失です。3年以内の早期離職では約1,500万円、ケースによっては3,000万円の損失が生じるとの試算も出ています。2つ目は指導力の損失です。採用しても定着率が悪い状態が続くと、「また辞めるのでは」とか「辞められたら困るので」と、描いていた育成計画の変更を余儀なくされたり、教育担当者も熱が入りづらくなります。一言で新人といっても中途採用の新人と新卒新入社員では違いがあります。
中途採用の場合は、経歴や実績からある程度先が見通せますが、新卒新入社員となるとなかなか先の見通しが難しく、期待外れもあるのではないでしょうか。そこで新卒新入社員の傾向と採用後の研修にフォーカスし、会社の将来を担う人財に育てるポイントを紹介します。
▼この記事でわかること
- 新人はビジネススキル不足・時間管理の未熟さ・不注意・思い込みが主な失敗
- 初めての失敗は成長のチャンス。否定せず受け入れ、原因を認識させることが大事
- 育成では、指示を「内容・目的・納期」などのポイントを押さえて明確に伝えること
- 明確な指示や振り返りを通じて、自発的に改善策を考えさせることが効果的
- 新入社員研修では、現場の仕事に直結しやすい「実務能力」より、「社会常識・人間関係」といった土台となる「態度能力」を優先!
- 研修後は目標意識とフォロー体制を整え、日常業務での定着を支援を
- 新入社員のよくある失敗
- 新入社員の失敗を防ぐために意識したいポイント
- 新入社員が社会人として成長するための4つの柱
- 新入社員研修を設計する際のポイント
- 新入社員が身に付けたい10の姿
- ハキハキ話す
- 質問には即座に答える
- 迅速に行動する
- 挨拶・返事を習慣にする
- 率直なコミュニケーションを取る
- 素直さ、謙虚さを持つ
- 5分前行動で、時間厳守する
- プラス思考でチャレンジする
- 常に明るい雰囲気をつくる
- 工夫・改善を継続する
- 新入社員研修を実施する際のポイント
- 研修後のフォローのポイント
- 新人・新入社員に対する「指導力」を身に付ける!おすすめ研修一覧
- 新人の失敗を成長の糧に。効果的な指導で即戦力化へ
- FAQ
新入社員のよくある失敗
ビジネススキルの不足
皆さんの会社で、このようなケースはないでしょうか。先輩社員や上司に対し誤った敬語を使ったり、クライアントや取引先のお客様よりも上座に座ってしまう。こういう振る舞いは、そもそも相手に対する敬意や礼儀に関する知識が不足しています。また簡単なコピーを頼んでも手間取ったり、電話対応が不慣れで相手を待たせてしまう。このようなケースは、往々にして消極的な姿勢が大きな原因です。“下手なことして失敗したらどうしよう“と、ためらって積極的に取り組むことを恐れてしまうからです。
新人の中には上下関係が厳しい部活に入り、礼儀を重んじる先生や先輩から敬語や順序を学んだり、アルバイトを通してお客様に対する積極的な対応力を身に付けた人もいるでしょう。しかし多くの学生は一番関わりを持つのは友達や仲間で、仲が良くなるにつれ仲間言葉を多用し敬語は死語になります。また専門学部以外は礼儀の知識や対応力は求められず、勉強しても就活前に付け焼き刃ていどなので、礼儀が出来ないのは当然です。
時間管理能力が未熟
出社時間に遅刻する、想定した時間内に仕事を終えられない、待ち合わせの時間や会議の時間に遅れる…このような新人に悩まされたことはないでしょうか。学生と社会人の大きな違いの1つがこれで、問題は時間に対する意識です。ビジネスでは時間厳守が重要で、遅れると信用を無くし得意先の取引がダメになったり大きな損失を被ることもあります。従って時間を守るためにはスケジュール帳に予定を書き込むだけでなく、万一のことを考え、間に合うように逆算して段取りを決める計画性が不可欠です。
ところが学生時代はどうでしょう。約束を守らず遅れても反発やハラスメントを気にするあまり「次から気をつけて」と、軽い注意で済まされ厳しく注意する人が減ってきています。家庭で躾られず学校で甘やかされると、約束や時間を守ろうとする意識が自ずと希薄になります。その結果、翌日に大事な予定があっても夜更かししたり寝坊したりと、多くの学生は計画性のない生活を毎日送り常態化したまま入社を迎えてしまいます。
不注意
仕事を任せても重要な数字を誤って入力する、商談の時間や曜日を勘違いする、ダブルブッキングする、重要書類を紛失する…このような不注意が多い新人は居ないでしょうか。どんなに優秀な人でもミスをしますが、これが多いとなると単なるミスでは済まされません。不注意が多いのは確認を怠るからですが、ではなぜ確認を怠るのでしょう。表面上の小さな原因は“面倒くさい”とか、“どうにかなるさ”と楽天的だからです。しかし深層上の大きな原因は、重要性を認識していないからです。
大事な試験や大事な試合なら、このようなことは滅多にないでしょう。重要なことは面倒くさがらず自ら確認するでしょう。しかし年々、社会で問題が起きる度に主催者責任を問われるケースが増えてきました。そこで主催者側は周知義務を果たすため、より丁寧に説明し数多く確認するようになってきました。学生にとって学校や先生は主催者側です。従って自ら確認しなくても、してもらえる環境の中で育ってきたことが背景要因です。
思い込み
上司からの指示をあいまいに受け取り、キチンと確認することなく行動に移してしまう…結果、初めからもう一度やり直さなければならない…と、このようなことはないでしょうか。それは上記の1~3までに挙げた原因がすべて当てはまりますが、それ以外にコミュニケーションの取り方も大きな要因です。相手と相互理解を図るには情報の共有だけでなく、意思と感情の共有も必要で、それらが上手く絡み合って初めてお互い理解し合えます。情報は資料、データや写真などツールを使って共有出来ますが、意思と感情はどうでしょう。
言葉は同じでも言い方や表情、仕草1つで全く意味や意図が違うことがあります。微妙なニュアンスは直接、対面でしか伝わりづらいものです。しかし今の時代の学生は、LINEなどのSNSを中心としたコミュニケーションツールを使ってのやりとりが多くなったため、反面、直接向かい合ってのコミュニケーションをとることが減ってきています。従って目の前で指示を出しても言葉だけキャッチしノンバーバルから意図をキャッチできず、結果上司との認識がズレやすくなっています。
新入社員の失敗を防ぐために意識したいポイント
初めての失敗は受け入れる
新入社員が初めて行うことや慣れていないことで失敗してしまうことはあります。そんな時、その失敗に気付いた先輩上司がどのように感じ、どのように受け止めるかが指導する上で大変重要なポイントになります。そのポイントは否定的か肯定的かで、ぜひ次のように肯定的な受け止め方を心がけてください。決して本人たちは悪気があってわざとしている訳ではありません。決してやる気がない訳ではありません。恥をかいて恥ずかしい思いをしているのは間違いなく本人です。初めて行うことや慣れていないことで失敗はつきものです。そして新入社員は多くの失敗から学び、成長していくものです。
今でこそ実績を残すようになった先輩上司たちも、新入社員時代を振り返ってみれば失敗談も必ずあるはずです。しかし、仕事が出来るようになった今の自分と新卒を比較すると「今年の新卒は全くダメ」と感じ、否定的に受け止めるようになります。すると、批判したり注意することばかりが先行してしまいます。誰でも比較するでしょうが、それは間違った比較であり、そこから間違った指導が始まります。比較するなら、自分の新入社員当時と比較してください。そうすると見方が変わります。受け止め方が変わります。先輩、上司として大事なことは新入社員の視点に立ち、先ずありのままの状況を受け入れること、これを基本としてください。
指示を明確にする
指示は本来明確であるべきですが、特に新人に初めての仕事を与える時は、より明確にする必要があります。逆に大雑把な指示や曖昧な指示を出すと不安が生じ、ミスや失敗を誘発させてしまいます。例えば「山田さん。書類の整理・整頓をしてください」と指示されても何処の書類? 何の書類? 何時まで?…と、様々な疑問が生じます。そんな時、積極的に質問して確認する新人も居ますが 多くの新人は“聞くのが恥ずかしい”とか、“聞くと仕事ができないと思われる”と、心理的な抵抗感から質問をためらってしまいます。
では明確な指示、逆に大雑把で曖昧な指示とはどんな指示でしょうか。先ず大雑把とは情報不足で、伝えるべきことに抜けがある状態です。そこで押さえておきたいのが「仕事を与える時の8つのポイント」です。指示を出す時は、①内容、②目的、③優先順位、④納期、⑤手順方法、⑥品質、⑦予算、⑧人員の8つをフォーマットとして念頭に置きましょう。次に曖昧とは、ぼかした状態です。「約」「ほど」「ぐらい」など余計な言葉を加えると曖昧になります。特に納期はシビアに「明日中」ではなく「明日の15時まで」とハッキリ伝えるべきです。指示の中身が複数の意味に受け取られないか意識し、認識の齟齬が起こらないように努めてください。
失敗の原因に気付かせる
新入社員は多くの失敗から学び、成長していくものです。またそうあって欲しいものです。しかし新人の中には、そもそも失敗を失敗と感じない人もいて、このままでは何も学べません。こういう場合は「本来は〇〇なのに…□□だね」と、あるべき姿と現状を告げて失敗をキチンと先ず認識して貰う必要があります。ただし失敗を失敗と認識して貰っても、笑顔で力強く「大丈夫です。次頑張ります!」と答えられると、その前向きさにつられ「期待してるよ」と、つい励ますだけで終わってしまうことはないでしょうか。チャレンジ精神は大事ですが、この繰り返しでは学べず成長できません。
失敗は問題ですから、解決するには原因と対策が必要です。なぜ失敗してしまったのか、新入社員に振り返らせることが大事です。そして自分の弱点を発見させ、改善策を考えさせることが必要です。そのためには上司が気付いたことを言うより「なぜ上手く行かなかったの?」と、聞いてください。すると言い訳など他責も言ってくるでしょうが、そこは我慢して口をはさまず自責が出るまでじっくり聞いてください。また改善策も同様に「どうすれば良かったの?」と、考えさせてください。自ら気付くと、自主的に取り組むようになります。
怒らずに指導する
初めての仕事の失敗は寛容な態度で受け止めても、同じ仕事で同じ失敗を繰り返されるとどうでしょう。時にはイライラをぶつけることはないでしょうか。これは残念ながら上司としては指導しているつもりでも、指導ではありません。本来“成長して欲しい”との思いや感情が、指導側にあるのが指導です。イライラしている時は、その思いや感情は消えているはずです。またイライラすると早口になり、言葉遣いが悪くなり、やがて質問が詰問に変わります。そうすると新人はプレッシャーから委縮し、何も答えられずダンマリ。その様子にイライラが高じ一方的に上から目線の説教が始まると最悪のパターンです。
こうなると、いくら言っていることが正論でも聞き入れられず、失敗を振り返り反省するより「何でそこまで言われなければ…」と、上司に不満やわだかまりが残り、心を閉ざしヤル気を失くします。また失敗の繰り返しでなく、大きなミスをしてしまった場合も同様です。新入社員も動揺しているので、一度心を落ち着けて冷静に対話してくだい。お互いが冷静になってこそ失敗の重大さや、改善の必要性に気付かせることができます。
新入社員が社会人として成長するための4つの柱
研修プログラムを構成する上で、重点を置きたい柱が4つあります。
- 一般素養や社会常識をわきまえること
- 人間関係能力を養うこと
- 会社や仕事の知識を増やすこと
- 実際に発揮する能力をつけること
この4つの柱が、社会人として新人が成長するための条件です。
新入社員研修を設計する際のポイント
新入社員研修の最大の目的
学生と社会人の大きな違いは立場の違いです。学生は学費を払う立場、社会人は給与を貰う立場です。この立場の違いによって意識や取るべき行動がガラっと変わります。学生時代は学費を払う立場ですから学校からすれば、学生はお客様です。お客様が居ないと会社は維持出来なくなるのと同様に、学校も経営難に陥り潰れます。
まして少子化が進むにつれ学生は取り合い。オープンキャンパスは至れり尽くせりで、入学してからも基本的には学生はお客様なので、余程の問題を起こさない限り丁寧に扱われます。学生の中には学費や生活費を親や親族の援助もなく、自力で稼ぎながら学業を励み卒業する学生もいます。
しかし多くの学生は少なからず親の援助を受け学費を出して貰います。それが悪いということではありません。問題は学費を出して貰っているにも関わらず、授業をエスケープし何事も適当に済ませ、お客様意識で過ごして来た学生です。
そんな学生が4月1日になった瞬間から、給与を貰う立場になります。貰うからには果たさなければならない責任を、責任感持って自らやり遂げなければなりませんが、このような社会人としての自覚が急に持てるようになるでしょうか。従って新入社員研修では、社会人としての意識と行動の切り替えを最大の目的とする必要があります。
態度能力を優先したプログラム
研修プログラムは上述した4つの柱に重点を置くのが大事なポイントですが、では4つの中で何を優先すべきでしょうか。これが次のポイントになります。
『一般素養や社会常識をわきまえること』『人間関係能力を養うこと』この2つを合わせて【態度能力】と呼び、一方『会社や仕事の知識を増やすこと』『実際に発揮する能力をつけること』この2つを合わせて【実務能力】と呼びます。
現場の仕事に直結しやすいのは実務能力です。従って早く戦力にと、事を急ぐと実務能力を優先したプログラムになりがちです。例えば、営業なら外回りの仕方や名刺交換の仕方、事務なら発注の仕方や請求書の作り方を教えようとします。
しかし、その前に態度能力を優先してください。社会常識が欠けていたり人間関係づくりが悪いと、職場で孤立し、お客様とのやりとりが上手く行かず、仕事で結果を出せず早期離職に繋がります。
生涯、一人で同じ仕事をやり続ける人もいるでしょう。しかし多くの社会人は、会社に入ってから部署が変わったり仕事が変わったりします。仕事によって必要とされる知識や能力も変わります。ところが仕事が変わっても社会常識や人間関係は生涯求められます。
実務能力と態度能力を「木」に例えると木が実務能力、根が態度能力です。想像してみてください。種を蒔いたら根から出ます。一般的な木は、根が3倍以上必要と言われています。根がダメなら木は育ちません。逆にしっかり大地に根を張った木は大きく育ちます。花が咲きます。実がなります。仕事ならその実が結果です。
研修の入口で心構えをつくる
研修のオリエンテーションで、新入社員に自己紹介と抱負を発表して貰うことが一般的には多いでしょう。その際の発表で、新入社員の心構えが良く掴めます。「何か一つでも学びたいです」「頑張って学びたいと思います」どうでしょう、こういった抱負をどう感じますか。
研修中も給与は発生するので研修は仕事です。仕事なら頑張るのは当たり前です。また研修は学びの場です。つまり厳しく捉えると具体的な抱負が何もありません。何のために研修を受けるのか目的を明確にしてきた人は「消極的な姿勢を改め積極的に質問して、礼儀の基本を学びます」と、自分の課題を必ず発表します。また意欲を持って受講する人は「…たいです」とか「…思います」ではなく「…します」とハッキリした意思表示をします。
このように僅か10秒~20秒の発表1つで、新入社員の心構えが掴めます。もちろん掴んだだけでは意味がなく、その場でしっかりとした抱負に改めて再度発表して貰うようにすると、真剣な姿勢に変わっていきます。
また研修中や研修の最後には、目標を決めて貰うと更に意欲が高まります。何をするかだけでなく、いつまでに、どのくらいするのか…と、①項目、②納期、③目標値この3つを明確にすることが目標です。目的を明確にすれば何をすべきかと、項目が浮かびます。
そこから納期と目標値を考え常に目的意識と目標意識を持って研修に臨んで貰うようにすると研修効果が随分違ってきます。初めから、これらを明確にして研修に参加する新人はどれだけいるでしょうか。多くの新人は、社会人としの意識の切り替えが不十分のまま研修に参加します。
だからこそ、研修の入口でしっかりとした心構えを持って貰うようにすることが必要になってきます。
礼儀・礼節を重視する
礼儀は社会常識と人間関係の基本で、けっしておろそかには出来ません。ところが時代とともに人は変わります。人が変われば礼儀も変わります。職場の中高年世代が育った時代なら、礼儀が悪いと近所の大人や祖父母などに叱られた経験を持つ方もいるでしょう。
しかし近所付き合いが薄れ、核家族化が進み、その上に共働きの親が増え礼儀を躾ける機会や時間が減って来ています。また学校では個人を尊重する風潮が高まり、頭髪や服装を含め校則がゆるやかになり、ルールや形を気にしない学生が増えて来ています。
ところがそんな環境で育った学生でも社会人になれば、それなりの礼儀が求められます。職場の先輩や上司、取引先や顧客に礼儀が求められます。また、コミュニケーションをとり意思疎通を図る対人関係力が求められます。従って研修では、そこに力点を置く必要があります。
研修中、話を聞く態度はどうでしょう。オリエンテーションで教育担当者が冒頭で挨拶をされた時、キチンと正対して背筋を伸ばし、目を見て時に頷きながら聞いているでしょうか。また自己紹介で発表する時、自分の番が終わっても他の人の発表をキチンと聞いているでしょうか。
これらは人に対する接し方の基本中の基本です。正対もせず目も見ず、足や手を組んだり、背もたれに寄りかかって聞いてないでしょうか。このような悪い聞き方をして、相手の話をキチンと受け止めないと、自分の話しも受け止めて貰えないということすら分かっていない新人もいます。
心構えが出来ても振る舞いが悪ければ、誤解されたり相手を不愉快にします。従って話す時、聞く時の態度や挨拶の基本が出来るような指導は欠かせません。「おはようございます」・「宜しくお願いします」・「ありがとうございます」・「お世話になります」・「はい、かしこまりました」・「申し訳ございません」・「お疲れ様でした」と、極めて基本的な態度や挨拶トレーニングを研修プログラムに入れてください。
そうすると、集中力と良い意味での緊張感が増します。そして何より研修に活気が出て、コミュニケーションが取りやすくなります。
新入社員が身に付けたい10の姿
ハキハキ話す
ボソボソ話すとヤル気がない印象を与えてしまい、周りの雰囲気を暗くします。対人関係で損することがあっても得することは何一つありません。自分の意見は、大きな声で語尾までハッキリ相手に伝えましょう。
質問には即座に答える
知っていることや自信のあることは即座に答えるでしょうが、そうでない時も即座に答えるのが礼儀です。沈黙が長いと、相手を不安にさせイラつかせます。従って基本的には2秒以内に答えましょう。
迅速に行動する
行動力のある人とは、決めたことや、決められたことをためらいなく行動に移す人です。直ぐやらないと後回しにしたり忘れたりします。特に仕事に取り掛かる時と、後片づけは意識してテキパキと進めましょう。
挨拶・返事を習慣にする
挨拶は「おはようございます」や「お疲れ様です」「失礼します」ばかりではありません。最も多く使うのは返事の「はい」です。声が掛かったり指示や説明を聞いている時、直ぐに感じ良く返事をすれば好印象です。
率直なコミュニケーションを取る
人間関係は心の交流です。報連相は仕事で大事なコミュニケーションですが、そればかりでは心の交流は図れません。気さくに声をかけ、その時々の心情も語ってください。心を開けば相手も開き、そこから交流が生まれます。
素直さ、謙虚さを持つ
上手く行くと自信が芽生えますが、過ぎると天狗になり成長しません。それは自分より下の人と比べるからです。上には上が居て上の人と比べる謙虚になれます。また注意されたら素直に非を認めるのも謙虚さの現れです。
5分前行動で、時間厳守する
5分前には準備万端で、仕事の開始と同時に100%の力が発揮できる状態にしましょう。お昼休憩も同じで5分前には午後の準備。また決めた時間を厳守するには、遅れて来た人を待たずに取り組む姿勢も大事です。
プラス思考でチャレンジする
始める前にネガティブなことをつぶやいたり愚痴ると、自分の力が発揮できないばかりか周りのモチベーションを下げます。どんな仕事を頼まれても「はい。喜んで」と、先ずポジティブな反応を示しましょう。
常に明るい雰囲気をつくる
人との会話は、明るい雰囲気で弾み暗いと沈みます。その明るさは笑顔と口調で決まります。出社前や訪問前には、鏡の前で口角を上げ自己チェックしましょう。また話す時はトーンを上げ明るい雰囲気をつくりましょう。
工夫・改善を継続する
仕事が終わり退社する前に1日を振り返りましょう。失敗した事や注意された事はもちろんですが、上手く行った事でも満足せず、もっと良くする方法を考え、メモに残し翌日の準備をして退社しましょう。
新入社員研修を実施する際のポイント
成長するための課題と対策を気付かせる
社会人として成長するための条件を先ず押さえます。社会常識や人間関係中心に学生時代を振り返って貰い、自己課題を気付かせ、それは何故か? どうすれば良いのか?…と、自ら成長するための方策を見つけて貰います。そして何事に対しても積極的に学ぶ姿勢をつくり、研修を受講する意欲を引き出します。
礼儀を学ばせる
人に対する接し方で重要なポイントは、相手を敬う心とキチンとした形で、この2つを振り返って貰います。相手を敬わず自分勝手になっていなかったか。また敬っていてもキチンをした形で接していたかどうか。その上で挨拶や立ち振る舞いは、良きモデルを示し実践トレーニングで好印象を与えるように指導します。
上司の役割を理解させる
上司は部下に仕事を与え、成長させる機会をつくります。しかし与えた仕事に対し意欲的に受ける部下も居れば、しぶしぶ受ける部下も居ます。仕事を覚える新人が、選り好みをしていては大きく成長出来ません。上司の役割を理解して貰い、どんな仕事にも意欲的に取り組む心構えと、仕事の受け方の基本姿勢をつくります。
ケジメをつけさせる
会社の備品を私物化したり、勤務時間中にPC使ってプライベートの検索をしたり、バレないように要領よく目先の利益に走るのは“けじめ”の無い無責任な行為です。ケジメとは何か?悪い要領を使うとどうなるか?誠実でキチンと規則を守り、自己抑制が利く社会人へと自覚を促します。
仕事の進め方を学ばせる
仕事を与えられた時、メモし復唱する事は仕事の受け方の基本です。また積極的に上司に質問し、疑問点を確認しておかないと期待通りの結果は出せません。何を確認するかはテーマ「指示を明確にする」でまとめた8つのポイントです。指示を出す上司も、受ける部下もお互い共通ポイントを押さえることで失敗は減ります。
基本的なビジネススキルを習得させる
顧客第一主義を理念に掲げる企業にとって、お客様対応力は必須です。ただし、その対応力は座学で知識を押さえた後にトレーニングをしないと身に付きません。来社された時のお迎え、お見送りの挨拶や、電話の出方や取次ぎもビジネスパーソンには欠かせない基本で、繰り返しのトレーニングで習得させます。
研修後のフォローのポイント
研修は人が変わるキッカケであり日常業務が本番です。従って研修を受けた新入社員がどのように変わったかを、教育担当者や上司は期待を持って見ることでしょう。また受講した新入社員もヤル気を持って次の日からの本番に臨んでくれることでしょう。しかし研修で学んだことが上手く活かせるとは限りません。目先の業務に気をとられ研修中に立てた目標を忘れたり、仕事でミスや失敗することもあります。そこで2つ気を付けて貰いたいことがあります。
目標を意識させる
1つはその目標です。研修中に目標を文章でまとめるだけでなく、それを机に貼ったり部署内で掲示したりと、常に目に入るようにすれば意識が働きます。また口に出して発表して貰うとさらに効果的です。逆に何もせず本人任せにすると、よほど意識の高い新人以外は忘れていくのが自然です。従って上司は目標を意識させる仕掛けをつくる必要があります。
ミスや失敗後の周りのフォロー
2つ目はミスや失敗からの落ち込みです。仕事には悩みがつきものですが、上手く解消する人とそうでない人がいます。上手く解消する人は落ち込みませんが、今の時代の新人はメンタルの弱い人が多くなり、落ち込むと厄介です。悩んだ時に上司に相談を持ち掛ける新人はまだしも、問題は相談したくても出来ない人です。
上司を信頼していても上司はあくまで上司なので、メンタルの弱い新人が悩みを打ち明けるには勇気がいります。従って上司から気さくに声を掛けてあげてください。また新人からすれば、悩みによっては身近な先輩の方が話しやすいこともあります。そこで新人を育てるのは上司だけの仕事とはせず、先輩も新人に積極的に声を掛けてあげてください。そしてその悩みに先ず共感したり、「私も新人の時は…」と失敗談を語ってください。新入社員と同じ目線で気持ちを受け止めれば、それだけでも心が晴れます。このように心のケアをしながら、新人を全員で育てる環境づくりが大きなポイントです。
新人・新入社員に対する「指導力」を身に付ける!おすすめ研修一覧
| 研修名 | 研修の特徴・ポイント |
|---|---|
| 管理者養成基礎コース | 新人育成に必要な管理者としての土台を築き、リーダーシップ・コミュニケーション・マネジメント能力を徹底敵に強化する合宿研修です。困難な訓練を通じて、逃げない姿勢と責任感、周囲を巻き込む行動的発想を体得します。 知識習得に留まらず、厳しい状況下で冷静に判断し、新人の成長と真摯に向き合う精神力とリーダーシップの基礎を養成し、指導者自身の意識と行動の変容を促します。 |
| 指導力開発訓練 | 部下育成の核となる「褒める」「叱る」「仕事を与える」の技術を、実践的なロールプレイングで集中的に訓練します。 特に、若手・新人の反発を恐れず、やる気を引き出す具体的な方法を体系的に習得。現場で即座に活かせる指導力を強化し、部下の自律性と早期戦力化を支援できるマネジメント力を養います。 |
| 現代の管理学Ⅰ | 管理者に不可欠なマネジメントの基本知識を体系的に学び、新人指導に必要な視点を強化します。目標達成のための仕組み、情報伝達の質と量の重要性、責任感の意識差を深く掘り下げます。 論理的思考力を鍛え、新人の特性に合わせた一貫性のある適切な目標設定や進捗管理を行う力を身に付け、場当たり的ではない本質的な育成を目指します。 |
| リーダーの条件 | 新入社員との信頼関係構築とやる気を高めるコミュニケーションに焦点を当てた研修。「正しく仕事を与える」「注意する」「誉める」というリーダーの基本動作をロールプレイで習得します。 断力や意思決定力を磨きながら、部門やチームを牽引できる実践的な力を身に付けます。 |
| MMS ヒューマンスキルコース | 人間力・対人スキルを重点的に鍛える研修です。コミュニケーション力、信頼構築力、部下指導力を体系的に学び、実務で応用できる技術として習得。 現代の職場に求められるリーダー像に沿った心理的スキルも強化し、部下や同僚との関係性改善と業績向上に直結します。 |
| 組織力向上研修 | チームや部門全体の生産性と協働力を高めるための研修です。組織内の役割理解、コミュニケーション改善、問題解決力を実践的に学習。 失敗を恐れたり不安を抱えている新人が活躍しやすい心理的安全性の高い職場環境を形成し、離職率低減や自律性を育む育成の土壌を築きます。 |
新人の失敗を成長の糧に。効果的な指導で即戦力化へ
新人・新入社員の成長プロセスにおいて、失敗は避けて通れない貴重な経験です。重要なのは、その失敗を「よくあるつまずき」として理解し、「学びの機会」に変えることにあります。また、効果的な指導や研修で新人の可能性を引き出すことで、組織全体の力も底上げできます。
なお、新人育成には、最新の傾向を踏まえた体系的なプログラムと、それを実行するノウハウが不可欠です。
社員教育のプロである「社員教育研究所」では、貴社の新入社員が抱える課題に合わせた実践的かつ効果的な研修をご提供し、企業の未来を担う人材育成を力強くサポートいたします。新人・新入社員の育成や研修に関してお困りの方はお気軽にご相談ください。
FAQ
新入社員がよくしてしまう失敗の主な原因は何ですか?
「ビジネススキルの不足」、約束や時間を守れない「時間管理能力の未熟さ」、仕事の重要性を認識しないことによる「不注意」、SNS中心のやり取りによる「思い込み」などが挙げられます。
新人の失敗をどう指導すれば成長につながりますか?
初めての失敗を否定せず肯定的に受け入れ、叱る・注意するよりも前に、新入社員の視点に立ってありのままの状況を受け入れることが基本です。
効果的な新人研修で重視すべきポイントは何ですか?
態度能力(一般素養・社会常識、人間関係力)を優先し、礼儀・心構え・目標意識を研修で習得させることが成長の鍵です。
この記事の監修者

株式会社社員教育研究所 編集部
1967年に設立した老舗の社員研修会社。自社で研修施設も保有し、新入社員から経営者まで50年以上教育を行ってきた実績がある。30万以上の修了生を輩出している管理者養成基礎コースは2021年3月に1000期を迎え、今もなお愛され続けている。この他にも様々なお客様からのご要望にお応えできるよう、オンライン研修やカスタマイズ研修、英会話、子供の教育など様々な形で研修を展開している。