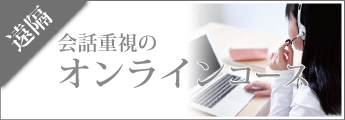マイクロマネジメントとは?部下を適切に管理し生産性を高める方法
カテゴリ:マネジメント
2022年2月14日(月)

リモートワーク・在宅勤務の普及などにより、マネジメントを行う管理者には新たなスキルや能力が求められています。そんななか、誤った管理方法と気づけず、過度な干渉や指示を出してしまう「マイクロマネジメント」を行うマネージャーも少なくありません。そのままでは、部下のポテンシャルが生かせないばかりか、組織力低下、売上げ減少といった影響が出る可能性も。そこでこちらでは、マイクロマネジメントの概要や陥る理由、回避・防止のためのポイントについて解説します。
育成力の重要性
マイクロマネジメントとは、組織や部下に対して、支配性の高いマネジメントを行う手法のことです。一般的にはネガティブなイメージで用いられており、管理者はマイクロマネジメントを行っている場合は、課題の一つとして捉えられます。
具体的な特徴についても見ていきましょう。例えば近年普及が進んだリモートワークでの場合。管理者がチャット等で進捗確認を行うのは至って普通のことです。しかし、マイクロマネジメントの場合はその頻度が高すぎてしまい、業務に支障が出てしまいます。また、「チャットやメールを見たら即レスポンス」といった返信ルールを半強制的に指示されていたり、社内及び外部へ送信するテキストに対して厳しいチェックが入ったりします。
こうした状況は、テレワークなどの非対面で組織を管理しなくてはならない場合に起こりやすいと考えられます。普段であれば適切なマネジメントを行えている管理者であっても、管理監督責任への不安から、無自覚にマイクロマネジメントを実行してしまう可能性もないとは言えません。
マイクロマネジメントは、会社のさまざまな場所に弊害や悪影響を及ぼす恐れがあります。
まずは組織全体。管理者の過干渉は、部下の労働意欲を低下させます。すると、組織全体の生産性低下にもつながり、利益にも関わるでしょう。また、過度な指示・命令によって部下のメンタルに負荷がかかり、体調不良やうつ病を引き起こす可能性も。ここまでいくと、部下の成長を阻害するだけはなく、転職を検討し始める、さらには労災などの問題にも発展しかねません。
また、管理者自身のパフォーマンス低下も懸念材料のひとつです。たとえば、部下が資料を作成したり進捗を報告したりすれば、それを上司は確認しなくてはなりません。マイクロマネジメントを行う管理者は、こうしたアウトプットにもしっかり目を通しがちです。すると、管理業務に時間が取られすぎてしまい、結果として上司のコア業務に支障をきたすおそれもあります。
マイクロマネジメントに陥る理由
管理者がマイクロマネジメントを行ってしまう理由として代表的なのが、部下の仕事に対する不安です。
管理者には管理監督責任があります。つまり、部下がミスをした場合には、上司である自分にも何らかの責任が発生します。また、その失敗が社内評価に影響することも少なくありません。
こうした状況を招かないためには、適切なマネジメントを行い、チームとしての成功を目指すのが本来です。しかし、リスクを過剰に恐れる上司の場合には、とにかく部下の仕事を細かく把握し、いろいろと指示を出して、ミスを防ごうとしてしまいます。その過度な干渉が、マイクロマネジメントにつながってしまうのです。
リモートワークを行う部下に対してのマネジメントは、近年になって求められるようになった業務のひとつです。非対面状況に置ける部下への仕事の働き方や工数コントロールなど。従来と性質が異なり、かつこれまで経験したことのない管理に四苦八苦するマネージャーも少なくありません。そこでマネジメントの実践方法や方針を間違ってしまうと、マイクロマネジメントを招く可能性があります。
部下の失敗をリスクと捉え過剰に心配する上司とは逆に、自分の成功のためにマイクロマネジメントを行ってしまう管理者もいます。こうした思いが強いマネージャーが率いるチームでは、より支配的な管理が行われています。
たとえば、自身の成功体験やアイデアを基にしたノウハウを資料にまとめ、チーム内で共有するのは一般的なマネージャーの業務と言えます。部下はその資料を参考に仕事を進められるため、業務効率化や目標達成などに寄与します。
しかし、マイクロマネジメントを行う上司の場合は、こうしたノウハウの実践を強要しがちです。異なる手順は認めず、強制的な指示を部下に出し続けてしまいます。また、指示のなかには非効率的かつ業務と関わりの薄いものなども含まれているケースが多く、結果として部下のリソースを奪ってしまいます。
マイクロマネジメントに陥らないための対策
マイクロマネジメントを回避するためには、部下を信頼して仕事を任せると共に、部下が自走しながら業務を進められる環境を作ることが大切です。そのためには、明確かつ達成可能な目標が求められます。こうした際に便利なのがSMARTの法則です。
抽象的な目標は部下を迷わせるだけです。主体的な行動を促すために、具体的な目標を立て、そこで向かうための詳細な道筋を分かりやすく示してください。
定性的な目標は達成基準が不明瞭になりがちであり、管理も難しくなります。そのため、目標達成の基準は必ず数値化するのが重要。進捗等も数字で可視化し、必要に応じて共有もしてください。
達成できない目標を掲げられても、多くの人は意欲を出せません。クリアできることが理解できるからこそ、そこに向かって努力ができます。そのため、目標が達成可能かどうか、はじめに上司が検証を行う必要があります。また、部下が弱気になっていたとしても頭ごなしに叱責せず、モチベーション向上のためのきちんと説明をすることが大切です。
達成感は人を動かす上で重要な要素のひとつではありますが、それだけではモチベーションが続きません。そこで、プロジェクトの成功が自分たちや組織に、どのような意味があり、利益をもたらすのかを伝えましょう。
部下の主体的な行動や態度変容を促すには、期限設定を行うのが効果的です。漠然としたスケジュールでは、計画は立ちません。デッドラインが決まればそこから逆算して仕事の進め方が導かれます。タイムリミットが意識できれば、自分が今何をすべきかも見えてくるでしょう。
マイクロマネジメントを引き起こす原因のひとつは、部下への信頼度の低さにあります。「自分の指示がないとミスをする」「仕事の進め方がよくない」といった気持ちが先行しすぎてしまうため、過干渉を行ってしまうのです。
こうした状況を改善するために第一歩は、部下の取り組みを信頼することです。そして、一人ひとりの気持ちに寄り添いながらマネジメントを行いましょう。「何か悩んでいることはないか?」とオープンクエスチョンを投げかけてみたり、相談を受けた際には聞き役に徹して、自分の価値観を押しつけないよう注意したり。接し方を変えることで、部下に対する理解が深まり、より強い信頼関係が築けます。
なお、それでも進捗や取り組みに不安を感じるようなら、無理のない頻度や回数を先に決めてしまいましょう。もしくは、ミーティングの開催も効果的です。現在の作業やネックになることを聞き出し、都度解決に向けた話し合いを行いましょう。
働き方に大きな変化がある時代。従来のマクロ的なマネジメント方法が通じなくなっているとお考えの管理者の方も多いでしょう。もしくは、最近管理職に就いたが、どのようにマネジメントを行えば良いか不安に思われている方もいるはずです。
「もしかすると、自分はマイクロマネジメントをしているのかも……」と感じているのなら、管理職向けのマネジメント研修参加がおすすめです。マイクロマネジメントの改善・防止はもちろん、現代で重要性が高くなったリモートマネジメント能力の向上も目指せます。
マネジメント研修やリーダー研修などに通い、リモートワーク時代のマネジメント力などを磨きたいとお考えの方は、ぜひ当社の研修をご活用ください。
「部下の成長を促すマネジメントを 」
マイクロマネジメントは、組織や部下に対して支配性の高いマネジメントを行う手法であり、回避・防止しなくてはなりません。リスクを過剰に恐れたり、成果に固執したり上司の場合は特に注意です。今回ご紹介したマイクロマネジメントに陥る理由、回避・防止のためのポイントを踏まえて、適切なマネジメントを行えるよう努めましょう。