新人教育担当必見!新入社員研修マニュアルの作り方
更新日:2025年10月20日(月)
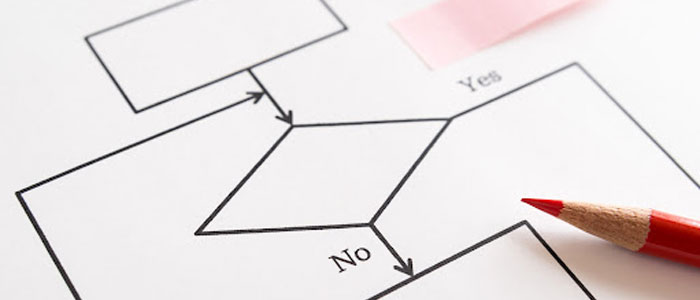
新入社員の研修にはいろいろな方法がありますが、どのような方法を採用するにしてもマニュアルがあると実施側・受講者側の両方にとってさまざまな面でプラスになります。
この記事ではマニュアルの作り方や使うときの注意点などについてまとめます。マニュアル作成を検討中の企業のご担当者様はぜひ参考にしてみてください。
▼この記事でわかること
- 新人教育の目的は、社会人マナー・業務スキル・企業理念や社内ルールの理解を通じて、短期間で戦力化を図る
- 新人研修方法の種類には、OJT、Off-JT、オンライン研修があり、組み合わせることで効果的な教育が可能
- マニュアルを活用することで、短期間で育成、作業の標準化、自力での確認ができ、研修効率が向上する
- マニュアル作成の手順は、PDCAサイクルに基づき、「内容の検討(Plan)」「具体的な形に落とし込み(Do)」「研修後のヒアリング・アンケートなど(Check)」「修正点の修正・改善(Act)」を繰り返して完成度を高める
新人教育の目的
まず、新人教育を行う目的について確認します。大まかに言うと、新人を短期間で戦力化することだと言えます。さらにその大きな目的を実現するために、より具体的な目的に細分化することができます。より具体的な目的としては、次の3点が挙げられます。
- 社会人としてのマナー・基本スキルの習得
- 業務を行うための知識・スキルの習得
- 企業理念や社内ルールの理解
1つずつ見ていきましょう。
目的|社会人としてのマナー・基本スキルの習得
まず、社会人としての最低限のマナーや基本スキルの習得が挙げられます。具体的には、電話の受け答え、名刺の渡し方、メールの書き方などのビジネスマナーなどです。ビジネスマンとしての基本に当たるものです。
マナーや基本スキルの習得は、主に新卒を対象に行われます。逆に言うと、基本マナーを教える余裕がない企業は中途採用を中心に採用していることになります。
目的|業務を行うための知識・スキルの習得
次に、業務を行うための知識・スキルの習得です。業種や職種によって必要な知識やスキルは異なり、具体的な内容は多岐に渡ります。例としては、営業トーク、接客方法、機械の操作方法、必要なPCソフトの使い方などが挙げられるでしょう。
業務上の知識・スキルを習得するための教育は、新卒はもちろん中途採用でも必要に応じて実施する必要があります。
目的|企業理念や社内ルールの理解
また、自社の社員が理解していなければいけない企業理念や基本姿勢、社内ルールなどを理解させることも目的の1つです。
企業理念や基本姿勢などは行動に影響するほか、そのやり方をする理由・背景の理解にも役立ちます。またより実務上の必要として、社内ルールも知っておかなくてはなりません。社員で当番制になっているもの、いろいろな申請や手続きの方法、備品の使い方、部屋や設備の配置、服装ほかさまざまなルールがあるでしょう。そのほか業務についても、自社特有のやり方などがあれば教えておく必要があります。
新人教育の具体的な方法
新人教育の具体的な方法についてまとめます。主な方法としては次の3つがあります。
- OJT
- Off-JT
- オンライン研修
いずれか単独ではなく、組み合わせて行うのが一般的かつ効果的です。それでは1つずつ見ていきましょう。
方法|OJT
「OJT」は「On-the-job Training」を略した形で、実際に業務を行いながら先輩が新人を教育する方法です。
メリットとしては、具体的なノウハウを学ぶことができる、新人の理解度に応じてスピードなど柔軟に対応できる、特別な準備が不要で費用がかからないといった点があります。現場の先輩たちとの人間関係の構築にも役立ちます。
ただし理論を体系的に学ぶのには不向きなこと、教育担当者の力量に成果が左右されることなどがデメリットだと言えます。
方法|Off-JT
「Off-JT」は「Off-the-job Training」を略した形で、セミナー形式・座学での教育です。研修と言うとこの形を連想する人が多いかもしれません。
一度に大人数の教育を行うことが可能です。また理論や理念などを体系的に学べること、新人同士の交流ができることもメリットです。
業務と離れて行うため、時間・場所を確保することが必要となります。人事担当者など自社の人物が講師を行う場合のほか、外注して外部の講師に依頼する場合もあります。外注するときも、自社に講師を招く場合と公開されているセミナーに赴いて参加する場合があります。
方法|オンライン研修
インターネットを使ったオンライン研修も近年導入例が増加しています。時間を決めてオンラインで講義を配信する形式や、学習者が自分のタイミングで学習できるeラーニングなどの形に分けられます。コンテンツは自社で用意する場合・サービス提供者が用意している場合などさまざまなパターンがあります。
場所を合わせる必要がないのが大きなメリットです。そのため移動費や会場費などのコスト削減につながります。eラーニングであれば時間すら合わせる必要がありません。
ただし実技を学ぶのには一般に向きません。また配信する側・学習する側のいずれもインターネットの設備が必要となります。
なお、弊社「社員教育研究所」では以下の研修をご用意しています
●オンライン若手研修
新入社員・一般社員向けに設計された2日間のオンライン研修です。社会人としての基本的な心構えから、日常業務で必要なコミュニケーション力やビジネスマナーまで、幅広く学べます。
単に聴くだけでなく、質問への回答や意見表明など話す機会を多く設けているのが大きな特徴。これにより、挨拶や報告・連絡・相談などの基本動作から上司や先輩の期待に応える仕事の受け方、さらには自分の意見を簡潔明瞭に伝える発言力の育成まで、実践的に学べます。
また、他の研修生の意見を聞く機会が多く、多様な価値観に触れることで自己理解を深め、組織で活躍するための視野を広げられる点も魅力です。
オンライン形式なので職場や自宅から参加可能で、時間や場所の制約なく効率的に学習できます。
新人教育とマニュアル
新人教育を行う際、マニュアルがあると効果的です。確かにマニュアルは研修の場面で使われることがあまりないかもしれません。しかし研修以外の場面では大いに役立ちます。
マニュアルがあると研修生も安心して作業を行うことができます。また教える側にとってもマニュアルの存在はさまざまな点でプラスとなります。
新人教育にマニュアルを活用するメリット
新人教育にマニュアルを活用するメリットをまとめます。具体的には以下の点が挙げられます。
- 短期間で育成できる
- 動作を標準化できる
- 自力で確認できる
1つずつ具体的に見ていきましょう。
メリット|短期間で育成できる
マニュアルを利用すると効率よく理解することができます。業務の手順が一通りまとめられており、なおかつ理解度に応じて活用することができるからです。
あらゆる作業についてまとめておけば、抜けなく作業内容を確認することができます。その際すぐに理解できたところは繰り返し確認する必要はありませんし、理解できないところはじっくり確認することができます。必要なポイントだけに集中することができるので、ムダな時間をかけることなく習得することができます。
メリット|動作を標準化できる
マニュアルによって動作を標準化することができます。属人的な勘や経験に頼るのではなく、誰がやっても基本的に同じ作業ができるようになります。
研修においては、「教える人によって言うことが違う」という事態を避けることが可能です。教育担当者も、どのような教え方をしたらいいのかに悩んだり迷ったりすることがなくなります。教え忘れや漏れもなくなります。
メリット|自力で確認できる
学習者・新人が自力で確認できるのも大きなメリットです。一度説明を受けたことを何度も尋ねることは、心理的に抵抗を感じてしまうものです。しかしマニュアルがあれば先輩や上司に尋ねることなく正しいやり方を確認できます。
また自力で確認できることは、教える側にとっても有益です。初めはやって見せたり説明したりして理解させることが必要ですが、それ以降は説明が不要になります。マニュアルを確認してもらえば、何度も業務を妨げられることがなくなります。
一度作って終わりではない
創業間もない企業など、初めての新入社員研修でマニュアルを作りたい場合も、また、ずいぶん前に作成したために見直しを検討している場合でも、マニュアルは一度作成して終わりではありません。なぜなら、時代に合わせた見直しや、実際に研修を行ってみたあとの反省点や改善点など、フィードバックの結果を反映させる必要があるからです。
たとえば、現代はかつての時代にはなかった、ITの普及による情報漏洩対策やコンプライアンス意識の強化が大切になっています。また、パワハラやセクハラの問題、子育て対策や働き方改革、ワークライフバランスやメンタルヘルス対策なども重要になっています。女性が働きやすい環境作りや、女性の管理職登用に向けたキャリアプランニングなども意識して、研修内容にも盛り込んでいく必要があるでしょう。
しかし、マニュアルは毎年時間と労力をかけて一から作り直すものでもありません。なぜなら、社会人としての礼儀やマナーなどの基本的なビジネスルールはいつの時代でも大きく変わることはなく、また、その企業の経営理念や創業精神、求める人物像などは頻繁に変わるものではないからです。
そのため、作成にあたっては基本となる部分の内容をしっかりと固めながら、時代の変化やニーズに合わせて少しずつ手を加えやすいスタイルで作成していくことがポイントになります。
新人への羅針盤を示そう
自社作成のマニュアルは、市販のビジネスマナー本や良きビジネスパーソンになるためのノウハウ本になってしまわないようにしたいものです。その会社で活躍し、キャリアを重ねていくうえでバイブルになるような内容に仕上げるのがベストです。
そのため、PDCAサイクルでプランニングするうえでは、次のような視点も踏まえ、人事部や配属先など会社全体の代表スタッフ、経営幹部なども巻き込んで話し合いなどを行い、検討することも大切になります。いつ頃までにどんなビジネスパーソンになってほしいのか、その際にどんなことを身に付けている必要があるかなど、キャリアプランを描いていきましょう。時期ごとの到達点を新人教育の羅針盤として設定することで、新人も目標が明確になり、モチベーションを高めて取り組むことができるようになります。
たとえば、入社して半年経った段階では周囲の協力を得ながら取引先とやり取りができるようになる、10ヵ月後には一人で顧客を任されるといった具合です。そして、そのためにはどのようなスキルを身に付け、どのような目標を立て行動すればよいのか、目標を達成するために必要なことを明らかにし、到達までの道筋もあらかじめ羅針盤として示すと、途中で挫折することなく進んでいくことができます。
基本的なテーマやおすすめの内容
そのほか、内容として組み込んでおきたい定番のテーマや内容は次のような項目です。
- ビジネスマナー・基本行動
- 仕事の進め方・姿勢
- コンプライアンス
- 業務の手順
- 企業理念・社内ルールなど
それぞれについて具体的に見ていきましょう。
テーマ・内容|ビジネスマナー・基本行動
ビジネスマナーと基本行動は押さえておきたい定番項目です。言葉遣いが学生気分のままでは、取引先や顧客、先輩社員とのコミュニケーションで失敗を起こしがちです。社会人としてのスキルを身につけさせましょう。短期間で戦力化するためには理解させておくことが欠かせません。
効率よく学習させつつ、確認しやすくするためにもマニュアルは効果があります。普遍性が高く企業による違いが少ない内容を含むので、研修の外注化や外部マニュアルの活用も比較的しやすい内容だと言えます。
テーマ・内容|仕事の進め方・姿勢
報・連・相など仕事の進め方の基本も、最初の段階でしっかり習得してほしいものです。報・連・相は基本のやり方は共通していますが、企業や部署、内容によって相手や手順が変わる場合もあります。自社での具体的な方法については個別にマニュアルを作成した方がよいでしょう。
仕事に取り組む姿勢も普遍的で共通する部分はありますが、経営方針やビジョン・ミッションによって違いがある場合もあります。自社の一員となる社員を育成するためには自社のマニュアルを作成することが大切です。
テーマ・内容|コンプライアンス
近年重要度を増しているコンプライアンスや、直ぐに辞めてしまう社員も多く問題になっているメンタルヘルスの管理方法やSOSの出し方なども学んでもらう必要があります。うかつなSNSでの発信や炎上動画の投稿をはじめ、顧客情報やクレジットカード情報などの流失、企業機密の漏洩やインサイダー取引の予防など、コンプライアンスをしっかり指導し、取り返しのつかないことが起こらないようにしたいものです。コンプライアンスで問題を起こせば、会社の信用が失墜するだけでなく、本人のキャリアにも大きくマイナスになり、会社を辞めざるを得ない事態にもなり得るからです。
コンプライアンスも業種や職種を問わず共通の内容が多いと言えますが、自社の事例をもとにした内容をプラスするとより身近に感じさせることができるでしょう。
テーマ・内容|業務の手順
マニュアルというと業務の手順をまとめたものを思い浮かべることが多いのではないでしょうか。作業の仕方や手順は業種や職種によって異なります。現場の声を集めつつ、自社ならではのノウハウを反映させてマニュアル化しましょう。
業務が多岐に渡る場合は、基本的な業務や重要な業務・標準化が必要な業務から優先的にマニュアル化を進めます。業務内容ごとに習熟度のステップを設定しておくと、評価基準と連動させることも可能です。
テーマ・内容|企業理念・社内ルールなど
マニュアルとは言いにくい面もありますが、企業理念もコンパクトな形でまとめておくと研修時に役立ちます。自社の社員としての自覚を育てるためには必須です。自社で作成しましょう。
社内ルールなどは比較的容易にマニュアル化が可能です。明文化しておくことをおすすめします。新人に限らず全社員が確認できるようになり、周知徹底に役立ちます。ただしルールに変更があったときは速やかに反映させる必要があります。
マニュアルを作る手順
マニュアルを作成するうえでも、またビジネスを効率的かつ生産的に行うにも、欠かせないPDCAサイクルを意識するとスムーズです。PDCAサイクルとは、Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Action(改善)を繰り返すことによって、生産管理や品質管理などの管理業務を継続的に改善していく手法のことです。
以下に、PDCAに基づくマニュアル作成の手順をまとめます。
手順➀ 内容の検討(Plan)
まずは第一段階のプランニングとして、どんな内容を盛り込んでいくのか、新人に求めるビジネススキルの整理や棚卸しを行いましょう。新入社員に知ってほしい、自社の仕事の概要を洗い出していきましょう。自社特有の業務やスキルの棚卸しとともに、社会人として身に着けておきたい、これからに役立つビジネススキルを整理します。
たとえば、仕事を合理的に進め、相手を納得させるための論理的思考力や仕事を効率的に進め、心身共に健康で仕事を継続するための自己管理能力、職場や取引先、顧客との仕事をスムーズに進めるうえで必須のコミュニケーション力、将来に向け目的を持ってステップアップしていくためのキャリアプランニングの立て方などを入れ込んでいきたいものです。
手順② 具体的な形に落とし込み(Do)
第二に整理した内容を具体的に落とし込む作業にとりかかります。作成にあたっては、フォーマットを決めておくのがベストです。今の時代、ほとんどの方がパソコンでデータとして作成し、管理されると思います。新入社員研修の担当者や作成者が変わっても、同じスタイルで踏襲できるようにフォーマットを決めておくと安心です。同じ作成者が作る場合も、その時の気分や内容によって、ページ構成が全く異なってしまうと見にくくなってしまいます。ページごとに体裁が違う内容では新人も分かりにくく、指導を担当する講師にとっても使い勝手が悪くなるので、統一的なスタイルで書けるようにフォーマットを作りましょう。既存のマニュアルがある場合はそのフォーマットで統一したり、共通したフォーマットを改めて見直すことをおすすめします。
フォーマットの作成や、実際の落とし込み作業で意識したいのは、文字ばかりを羅列するのではなく、画像やイラスト、図やグラフなど視覚的に見て直ぐに分かりやすいものを用いることです。大量の文章が並んでいても頭にスッと入ってこないので、ポイントを箇条書きなどにまとめ、あとは講師が口頭で具体的に説明するスタイルにするのもひとつの方法です。また、文章をベースにする場合も、内容のポイントをまとめた囲み図や、イラストを用いた図解を入れ込むとメリハリがつきます。
手順③ 研修後のヒアリング・アンケートなど(Check)
第三段階でのチェックは、新入社員研修実施後にフィードバックを行うようにします。新人受講生の反応はどうだったのか、しっかり理解してもらえたか、研修に満足度や充実感を得てくれたか、研修の内容が職場へ配属後に行かされているか、などをチェックしましょう。受講した新人からのアンケートや生の声を聴いたり、講師からも研修の様子や講義後の意見を聞いてみましょう。
さらに職場配属後にそれが活かされているか、足りないことや研修でもっと強化してほしいと感じた点はなかったかなど、現場の声も聞きましょう。同時に、配属先の部門長や新人育成担当スタッフ、先輩社員たちの声をヒアリングします。また、配属後、少し期間が経った段階で、受講した新人から研修内容が役立っているか、もっと事前に学べたら良かった点はあったか、といったアフターフィードバックも得るといいでしょう。
手順④ 修正点の修正・改善(Act)
そして、第四段階として次年度の新入社員研修に向けて、フィードバックしたポイントをマニュアルに反映させて改善を図ります。この際の改善や改定のためのメンテナンスのルールも決めておくと安心です。メンテナンスのタイミングとして、研修実施後にフィードバックを反映することと、年度末などに社会の流れや会社の仕組みの改変などに合わせた改定を加える計画を立てておきましょう。
マニュアルを使用するときの注意点
作成したマニュアルを使用するときの注意点についてまとめます。具体的には以下の点が挙げられます。
- 背景となる考え方にも触れる
- 教える側がマニュアルを否定しない
- マニュアルにこだわりすぎない
それぞれについて見ていきましょう。
注意点|背景となる考え方にも触れる
まず動作の手順ややり方だけでなく、その背景となる考え方や理由などについて触れるような形でまとめましょう。考え方もセットで学ぶことで、理解が深まりミスや規定の方法から外れるのを減らすことができます。
また未知のことに対応せざるを得なくなったとき、考え方を理解していると自分で考えて対応できるようになります。より高い対応力や応用力も育ちます。
注意点|教える側がマニュアルを否定しない
教える側がマニュアルを否定しないことも大切です。「本音と建て前」のように、「実際はこのようにはやっていられない」「現場を知らない人が作った」などと話してしまうと、マニュアル軽視の空気ができてしまい作業の標準化が進みません。
ただしマニュアルとしての完成度・精度を高めて実際に役立つものとする努力は必要です。いきなり完全なマニュアルを作ることは難しいですが、絶えず完成度を高めることは意識しましょう。
注意点|マニュアルにこだわりすぎない
マニュアルを否定しないということと矛盾するようですが、マニュアルにこだわりすぎないことも重要です。予期しなかった変化や不測の事態が発生して、マニュアルに反映させなくてはいけなくなるかもしれません。あるいはよりよい手順を思いつくかもしれません。
背景となる根本的な考え方と押さえなくてはならないポイントは説明・指導して、そのほかの点については徐々に習得させるぐらいの姿勢の方が適切かもしれません。短期間で合格レベルまで育成しやすくなるほか、マニュアル以外のこと・マニュアル以上のことのできない社員を生むリスクを減らすことができます。
教育担当者への対応
社員教育を成功させるためには、現場で教育に当たる担当者の理解と協力が必須です。現場の教育担当者にどのように対応したらよいかをまとめます。次の点が挙げられます。
- 「任される理由」を伝える
- 期待や担当することへのメリットを伝える
- 教え方・心構えを身に付けさせる
- 業務量を調整する
1つずつ見ていきましょう。
対応|「任される理由」を伝える
教育担当者には、教育を任せる理由を伝えましょう。教育担当者として選んだからには、適任だと考えた理由があるはずです。実務を理解している・手本となる結果を出しているといったことに加え、教育に向くコミュニケーション能力などが見込まれることが多いでしょう。
新人教育の重要性とともに、適任だと考えた理由を伝えましょう。
対応|期待や担当することへのメリットを伝える
教育担当者としての期待や、担当することによって本人にどのようなメリットがあるかも伝えます。負担だけでないことを理解させましょう。
任せる理由ともつながりますが、担当者はリーダー候補であることも多いのではないでしょうか。上司となったときの部下の育成方法を学ぶことができること、業務を改めて把握するきっかけとなることなど、担当者としての経験を通じて得られるメリットを伝えましょう。
対応|教え方・心構えを身に付けさせる
現場の社員が教育を担当する場合、ネックとなるのが担当者による内容や質のブレです。担当者本人も教え方がわからないという不安を抱えがちです。ブレや不安を防ぐために、教育担当者として求められるスキルや心構えを習得させましょう。
理解しやすい教え方や、想定される質問やつまずきやすいポイントとその対応などをあらかじめ伝えておきます。また新人が安心して研修に臨めるようにするためには、威圧的な態度を取ることやいら立つことなどは厳禁です。ひどい場合には離職につながってしまう可能性があります。一度教えたからと言ってすぐにはできるようにならないといった心構えも教えておく必要があります。
対応|業務量を調整する
現場の社員が担当者となる場合、教え方のほか業務の量に不安を感じることが多くあります。可能な範囲にはなりますが、教育に当たることを考慮してそのほかの業務の量を調節するなど対処しましょう。
また周囲のほかの社員に対しても理解を求めることが大切です。新人の教育は会社の将来性にかかわる重要な業務です。全社で取り組む必要があり、それぞれがそれぞれの立場で貢献することが必要だという共通の認識を持たせましょう。
【新人向け】おすすめ研修一覧
新入社員として社会人生活をスタートするにあたり、基礎力や行動力をしっかり身につけることが重要です。ここでは、仕事の基本マナーからチームでの協働力、問題解決力までを体系的に学べる社員教育研究所の新人向け研修を厳選してご紹介します。
| 研修名 | 研修の特徴・ポイント |
|---|---|
| フレッシュマン颯爽研修 | 社会人としての基本姿勢やビジネスマナーを短期間で集中学習。 チームワークや報連相の習慣化を通じて、即戦力としての基礎を身につけます。 |
| GO!フレッシュマン現代の行動学 | 新人として職場で求められる行動力や課題発見力を実践的に習得。 ケーススタディやロールプレイを通じて、自ら考え行動できる力を養います。 |
| 新人行動力研修 | 「話す・問題を発見する・人間関係を築く」の3項目を徹底強化。 体験型の合宿研修で、実践的な報告・相談・協調のスキルを習得し即戦力化を目指します。 |
【教育担当者向け】おすすめ研修一覧
新人教育を担当する方にとって、指導力や管理能力を高めることは欠かせません。ここでは、部下育成やコミュニケーションスキル、管理職としての実践力を磨ける研修を中心にご紹介します。
| 研修名 | 研修の特徴・ポイント |
|---|---|
| 管理者養成基礎コース | 管理者向けに、部下育成・目標管理・業務改善など、管理職に必要な基礎スキルを体系的に学習。 職場での指導力向上をサポートします。 |
| 指導力開発訓練 | 部下への効果的な指示出しやフィードバック方法、モチベーション管理を習得。 ロールプレイを通じて現場で活かせる指導力を鍛えます。 |
| MMS ヒューマンスキルコース | 部下育成指導力と顧客対応力の両方をバランスよく習得。 職場でのアウトプットも組み合わせ、リーダーとしての実践力を高めます。 |
新人教育を成功させよう
新人教育は自社の将来を決める一因ともなる重要なものです。効果的に行うことができるよう、万全の体制を整えましょう。
効果的な新人教育を行うためには、専門のサービスを利用してプロに任せるという手段もあります。自社で行う場合も、担当者にコーチングなど教育方法の研修をしておくと効果が高まります。とくに一般の社員が教育に関わる場合は、属人的になることを避けるための仕組み作りがカギとなります。
当社では、先にご紹介した研修をはじめ、教育に役立つ研修を複数ご用意しています。ご興味がおありならぜひご連絡ください。ページ上部に連絡先があります。お気軽にご相談ください。
FAQ
新入社員研修の目的は?
社会人マナーの習得、業務スキルの向上、企業理念や社内ルールの理解を通じて、新人を短期間で戦力化することが目的です。
新人研修マニュアルの作成で重視すべき点は?
動作や手順だけでなく、背景や考え方も明確にすることです。また、時代の変化や研修実施後のフィードバックを反映させるため、基本を固めつつ、修正・改善しやすいスタイルで作成することが重要です。
教育担当者が新人教育を成功させるために必要なことは?
教育担当者には、教育を任せる理由やメリットを伝え、教え方や心構えを習得させるとともに、教育に当たることを考慮して業務量を調整するなどの配慮が必要です。
この記事の監修者

株式会社社員教育研究所 編集部
1967年に設立した老舗の社員研修会社。自社で研修施設も保有し、新入社員から経営者まで50年以上教育を行ってきた実績がある。30万以上の修了生を輩出している管理者養成基礎コースは2021年3月に1000期を迎え、今もなお愛され続けている。この他にも様々なお客様からのご要望にお応えできるよう、オンライン研修やカスタマイズ研修、英会話、子供の教育など様々な形で研修を展開している。









